高額療養費の給付について
高額療養費の償還について
同じ月内に医療機関に支払った医療費の自己負担額が、自己負担限度額(世帯の所得段階に応じて定められた、自己負担の上限額)を超えた場合、高額療養費支給の申請をすることができます。
支給額は自己負担額から自己負担限度額を引いた額となります。
算定の結果、1,000円以上の支給対象となる方については、世帯主あてに「高額療養費支給申請書」を郵送しますので、申請してください。
申請に必要なもの
- マイナ保険証等
- 高額療養費支給申請書
- 振込先金融機関・口座番号等がわかるもの
自己負担限度額について
70歳未満の方の場合
自己負担額計算上の注意
1.月の初日から月末までの1か月の診療ごとに計算します。
2.食費や居住費、保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外です。
3.ひとつの医療機関ごと(入院・外来・医科・歯科別)に計算します。
4.院外処方で調剤を受けたときは処方箋が出された医科(歯科)の自己負担額と合算します。
5.個人ごと、ひとつの医療機関ごと(入院・外来・医科・歯科別)に21,000円以上の支払いがあったものが計算の対象です。
| 適用区分 | 所得区分 | 自己負担上限額(月額) |
|---|---|---|
| ア | 所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
| イ | 所得600万円超から901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
| ウ | 所得210万円超から600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
| エ | 所得210万円以下 | 57,600円 |
| オ | 住民税非課税(注1) | 35,400円 |
過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の該当が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は軽減されます(多数回該当)。
4回目以降の自己負担限度額(月額)
| 適用区分 | 所得区分 | 自己負担上限額(月額) |
|---|---|---|
| ア | 所得901万円超 | 140,100円 |
| イ | 所得600万円超から901万円以下 | 93,000円 |
| ウ | 所得210万円超から600万円以下 | 44,400円 |
| エ | 所得210万円以下 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税(注1) | 24,600円 |
(注1)同じ世帯の世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の方
70歳以上の方の場合(70歳から74歳)
自己負担額計算上の注意
1.月の初日から月末までの1か月の診療ごとの計算します。
2.食費や居住費、差額ベッド代などは支給の対象外です。
3.ひとつの医療機関ごと(入院・外来・医科・歯科別)に計算します。
4.院外処方で調剤を受けたときは処方箋が出された医科(歯科)の自己負担額と合算します。
5.外来では個人ごとに計算します。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 |
現役並み3 課税標準額690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | |
|
現役並み2 課税標準額380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | ||
|
現役並み1 課税標準額145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | ||
| 一般 |
18,000円 (年間144,000円上限(注1)) |
57,600円 | |
| 住民税非課税 | 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得1 | 15,000円 | ||
(注1)年間とは毎年8月から翌年7月までの期間です。
過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の該当が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は軽減されます(多数回該当)。
4回目以降の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 |
現役並み3 課税標準額690万円以上 |
140,100円 | |
|
現役並み2 課税標準額380万円以上 |
93,000円 | ||
|
現役並み1 課税標準額145万円以上 |
44,400円 | ||
| 一般 | 18,000円(注1) | 44,400円 | |
| 住民税非課税 | 低所得2 | 8,000円(注1) | 24,600円(注1) |
| 低所得1 | 15,000円(注1) | ||
(注1)所得区分一般世帯の外来および所得区分非課税世帯については、多数回該当の適用外です。
限度額適用認定証について
入院などにより医療費が高額になる場合、あらかじめ申請をして「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額認定証)」の交付を受けておくと、医療機関での支払いを所得区分ごとの自己負担限度額にとどめることができます。
なお、70歳から74歳で所得区分が「一般」もしくは「現役並み3」の方については、マイナ保険証等を医療機関の窓口で提示することで、医療機関での支払いを所得区分ごとの自己負担限度額にとどめることができるため、限度額適用認定証の交付を受ける必要ありません。
- マイナンバーカードに健康保険証を連携するとマイナ保険証として利用できます。マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額認定証)の発行は不要で、医療機関での支払いを所得区分ごとの自己負担限度額にとどめることができます。
- 国民健康保険に滞納がある場合は、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額認定証)の発行ができない場合がありますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- マイナ保険証等
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カードなど)
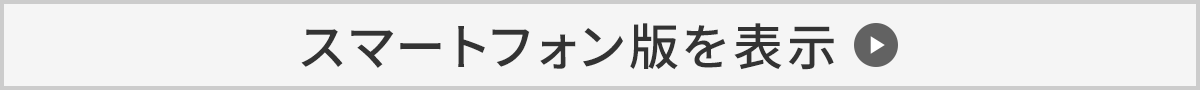








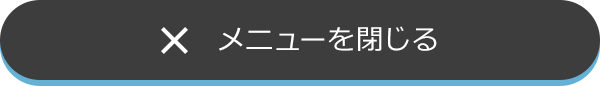




更新日:2024年12月02日