福祉医療費助成事業
福祉医療費助成制度は保健の向上と福祉の増進を図るため、健康保険に加入する乳幼児や重度障害者(児)などの自己負担分の一部または全部を助成する制度です。保険適用外料金、交通事故等の第三者行為による治療費には助成できません。また、他の公費、保険者から給付される高額療養費・附加給付金等は福祉医療助成費から除きます。
なお、申請が遅くなると申請月からの助成となり、遡って助成できない場合がありますのでご留意ください。
それぞれの制度については、次のとおりです。
乳幼児
対象となる人
就学前までの乳幼児
自己負担の有無
保険診療内の自己負担はありません。
申請に必要なもの
マイナ保険証等(出生児の場合は、加入予定の方のもの)
所得制限の有無
なし
小中学生
対象となる人
小学1年生から中学3年生
自己負担の有無
保険診療内の自己負担はありません。
申請に必要なもの
マイナ保険証等
所得制限の有無
なし
高校生世代
対象となる人
義務教育終了から18歳になり最初の3月31日まで
自己負担の有無
保険診療内の自己負担はありません。
申請に必要なもの
マイナ保険証等
所得制限の有無
なし
重度障害者(児)
対象となる人
- 身体障害者手帳1級から3級の人
- 療育手帳A・Bの人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
- 身体障害者手帳3級、療育B1、精神障害者保健福祉手帳2級のうち2種類の手帳を持つ人
- 特別児童扶養手当支給対象児童で障害の程度が1級の人
自己負担の有無
通院
1診療報酬明細あたり500円
ただし、助成対象者・配偶者・扶養義務者のいずれも住民税が課税されていない場合、または助成対象者が小中学生の場合は、自己負担はありません。
入院
1日あたり1,000円(月額14,000円が上限)
ただし、助成対象者・配偶者・扶養義務者のいずれも住民税が課税されていない場合、または助成対象者が小中学生の場合は、自己負担はありません。
申請に必要なもの
- マイナ保険証等
- 身体障害者手帳または療育手帳または特別児童扶養手当証書
※課税・非課税証明書
転入などにより湖南市で所得が確認できない場合のみ、前住所地などでの課税・非課税証明書(所得額と控除額等が詳細に記載されているもの)が必要です。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
所得制限の有無
あり
※本人だけでなく配偶者・扶養義務者にも所得制限があります。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
低所得老人(65歳から74歳)
対象となる人
本人および配偶者・扶養義務者等のすべてが住民税非課税の人
自己負担の有無
保険診療内は1割または2割負担となります。
申請に必要なもの
- マイナ保険証等
※課税・非課税証明書
転入などにより湖南市で所得が確認できない場合のみ、前住所地などでの課税・非課税証明書(所得額と控除額等が詳細に記載されているもの)が必要です。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
所得制限の有無
あり
※本人だけでなく配偶者・扶養義務者にも所得制限があります。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
母子家庭
対象となる人
配偶者のない女子が18歳未満の子を扶養しているときの母とその子
自己負担の有無
通院
1診療報酬明細あたり500円
ただし、助成対象者・扶養義務者のいずれも住民税が課税されていない場合、または助成対象者が小中学生の場合は、自己負担はありません。
入院
1日あたり1,000円(月額14,000円が上限)
ただし、助成対象者・扶養義務者のいずれも住民税が課税されていない場合、または助成対象者が小中学生の場合は、自己負担はありません。
申請に必要なもの
- マイナ保険証等
- 児童扶養手当認定通知書または母子家庭証明書
規定の様式がありますので、詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
※課税・非課税証明書
転入などにより湖南市で所得が確認できない場合のみ、前住所地などでの課税・非課税証明書(所得額と控除額等が詳細に記載されているもの)が必要です。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
所得制限の有無
あり
※本人だけでなく扶養義務者にも所得制限があります。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
父子家庭
対象となる人
配偶者のない男子が18歳未満の子を扶養しているときの父とその子
自己負担の有無
通院
1診療報酬明細あたり500円
ただし、助成対象者・扶養義務者のいずれも住民税が課税されていない場合、または助成対象者が小中学生の場合は、自己負担はありません。
入院
1日あたり1,000円(月額14,000円が上限)
ただし、助成対象者・扶養義務者のいずれも住民税が課税されていない場合、または助成対象者が小中学生の場合は、自己負担はありません。
申請に必要なもの
- マイナ保険証等
- 児童扶養手当認定通知書または父子家庭証明書
規定の様式がありますので、詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
※課税・非課税証明書
転入などにより湖南市で所得が確認できない場合のみ、前住所地などでの課税・非課税証明書(所得額と控除額等が詳細に記載されているもの)が必要です。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
所得制限の有無
あり
※本人だけでなく扶養義務者にも所得制限があります。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
ひとり暮らし寡婦
対象となる人
配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として18歳未満の子を扶養していたことのある者で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続し、今後もその状態が継続する65歳未満の人
自己負担の有無
通院
1診療報酬明細あたり500円
ただし、助成対象者・扶養義務者のいずれも住民税が課税されていない場合は、自己負担はありません。
入院
1日あたり1,000円(月額14,000円が上限)
ただし、助成対象者・扶養義務者のいずれも住民税が課税されていない場合は、自己負担はありません。
申請に必要なもの
- マイナ保険証等
- ひとり暮らし寡婦申立書
規定の様式がありますので、詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
※課税・非課税証明書
転入などにより湖南市で所得が確認できない場合のみ、前住所地などでの課税・非課税証明書(所得額と控除額等が詳細に記載されているもの)が必要です。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
所得制限の有無
あり
※本人だけでなく扶養義務者にも所得制限があります。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
ひとり暮らし高齢寡婦
対象となる人
配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として18歳未満の子を扶養していたことのある者で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続し、今後もその状態が継続する65歳から74歳の人
自己負担の有無
保険診療内は1割または2割負担となります。
申請に必要なもの
- マイナ保険証等
- ひとり暮らし高齢寡婦申立書
規定の様式がありますので、詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
※課税・非課税証明書
転入などにより湖南市で所得が確認できない場合のみ、前住所地などでの課税・非課税証明書(所得額と控除額等が詳細に記載されているもの)が必要です。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
所得制限の有無
あり
※本人だけでなく扶養義務者にも所得制限があります。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
重度障害老人
対象となる人
後期高齢者医療制度の加入者で次の人
- 身体障害者手帳1級から3級の人
- 療育手帳A・Bの人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
- 身体障害者手帳3級、療育B1、精神障害者保健福祉手帳2級のうち2種類の手帳を持つ人
自己負担の有無
通院
1診療報酬明細あたり500円
ただし、助成対象者・配偶者・扶養義務者のいずれも住民税が課税されていない場合は、自己負担はありません。
入院
1日あたり1,000円(月額14,000円が上限)
ただし、助成対象者・配偶者・扶養義務者のいずれも住民税が課税されていない場合は、自己負担はありません。
申請に必要なもの
- マイナ保険証等
- 身体障害者手帳または療育手帳
※課税・非課税証明書
転入などにより湖南市で所得が確認できない場合のみ、前住所地などでの課税・非課税証明書(所得額と控除額等が詳細に記載されているもの)が必要です。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
所得制限の有無
あり
※本人だけでなく配偶者・扶養義務者にも所得制限があります。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
受給券(助成券)の交付について
申請に必要なものを持って保険年金課で申請してください。
医療費助成を受けるには
【県内での受診】
医療機関の窓口でマイナ保険証等と福祉医療受給券(助成券)を一緒に提示することで、医療費(保険診療内)の自己負担分の助成が受けられます。
【県外での受診】
福祉医療受給券(助成券)は県外の医療機関では使えません。いったん、医療費(保険診療内)の自己負担分を支払い、後日、1か月分をまとめて保険年金課へ請求してください。
請求に必要なもの
- 領収書(氏名、領収額、診療点数、領収年月日の記載がないと支給できませんので、必ず医療機関で書いてもらってください。)
- 振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード)
- 福祉医療受給券(助成券)
- マイナ保険証等
- 加入する健康保険組合から高額療養費、附加給付が支給されている場合はその支給決定通知書
次の場合には届出を
(1)住所・氏名の変更
受給券(助成券)を持って届け出てください。
(2)健康保険の変更
1 窓口申請
- マイナ保険証を紐づけている人は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせ(資格情報通知書)
- マイナンバーカードを持っていない人、保険証と紐づけていない人は、資格確認書もしくは有効期限内の健康保険証
と受給券(助成券)持って届け出てください。
2 電子申請
下記のフォームから申請してください。
https://logoform.jp/form/AMUY/1313494
(3)受給券(助成券)を紛失や汚損した場合
身分証明書をもって再交付の申請をしてください。
(4)転出されたとき、受給券(助成券)の有効期間が切れたとき
助成対象者でなくなったときは、受給券(助成券)は使用できません。必ず保険年金課へご返却ください。
高額療養費に該当した場合
受給・助成対象者の医療費は、いったん高額療養費も含めて湖南市の福祉医療制度が負担します。いったん負担した高額療養費は、湖南市から健康保険の保険者に請求します。この請求にあたっては、被保険者からの委任が必要となります。該当者には、委任状も含んだ申請書を送付しますので、申請書が届いたら速やかに必要事項を記入し押印して提出してください。
また、一部の健康保険組合などでは、申請がなくても自動的に被保険者に高額療養費を支払われる場合があります。湖南市の福祉医療制度からの助成と高額療養費の支給を二重に受け取ることはできませんので、健康保険から高額療養費を受け取った場合は、湖南市から対象者に高額療養費返還の請求をします。請求があったら、速やかに返還してくださいますようお願します。
高額療養費制度とは
ひと月に負担する医療費は、上限(自己負担限度額)が定められています。その上限を超えた場合、超えた分を加入している健康保険が負担する制度です。
附加給付があった場合
一部の健康保険組合などでは、法律で定められた保険給付と併せて、一部負担還元金や家族療養費付加金などの附加給付が支給される場合があります。そのような支給を受けられたときも、湖南市の福祉医療制度からの助成と二重に受けることはできません。健康保険から支給があった場合や湖南市で確認ができて助成分の返還の請求があった場合は、速やかに返還してくださいますようお願いします。
日本スポーツ振興センターからの災害給付金を受けた場合
福祉医療費受給券を提示してかかられた診療分について、日本スポーツ振興センターから給付金(医療費3割+見舞金1割)を受けられた場合は、福祉医療制度からの助成と二重に受け取ることはできません。湖南市から助成分の返還の請求があった場合は、速やかに返還してくださいますようお願いします。
年度更新について
乳幼児・小中学生以外の制度(受給券(助成券)の有効期間:7月31日まで)
毎年8月に更新手続きが必要です。所得制限がありますので、前年所得の確認を行い該当者には手続き方法について通知します。所得制限を超えられると、その年度(8月1日から翌年7月31日まで)は助成を受けることができません。
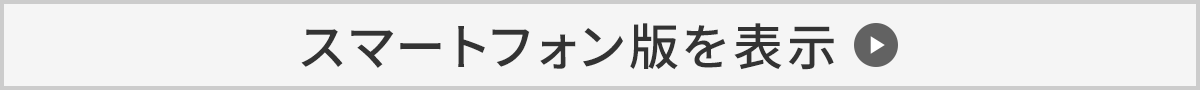








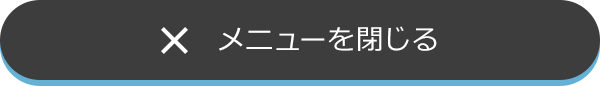




更新日:2025年11月20日