令和5年度第3回湖南市地域公共交通会議会議録
湖南市地域公共交通計画(案) (PDFファイル: 14.6MB)
日時 令和6年3月25日(月曜日)午後3時00分から
場所 湖南市役所東庁舎3階 大会議室
出席者 委員23名(欠席5名)事務局7名
議事
〇協議事項
「湖南市地域公共交通計画」の策定について
〇その他
|
日時 |
令和6年3月25日(月曜日)15:00~15:47 |
|
場所 |
湖南市役所 東庁舎 3階 大会議室 |
開会
事 務 局:委員28名中23名の出席があり、過半数を超えていることから、会議は成
立している。
1.あいさつ
会 長:いよいよ来週から4月となり、2024年問題の現実に突入する。2025年問
題はもっと大きくなる。バス運転手不足は今後も続いていく。これを解
決しない限り、現状以上のネットワーク充実は難しい状況にある。人口
減少状況にある中山間地域ならまだしも、これだけ人口のある湖南市で
も運転手の担い手がいないのか。根本的な問題は、各セクターの方でも
お考えいただきたいし、本会議でも、何が問題か明らかにしていかない
限り、担い手不足問題は解決しない。次年度以降、この深刻な問題に対
し、皆様から様々にご意見をいただきたい。
2.議事
(1)協議事項
第1号議案 「湖南市地域公共交通計画」の策定について(資料1、2)
事 務 局:資料1、2、資料「湖南市地域公共交通計画(案)」により説明。
会 長:質問、意見はあるか。
委 員:コミュニティバスのダイヤ改正にあたり、ぎりぎりまでご努力いただ
き、一部便を存続いただいたことに感謝する。「湖南市地域公共交通計
画(案)」には異議はない。「その他」で発言しようかと思ったが、パ
ブリックコメント結果についてご説明があったため、ここで発言する。
美松台ルートに対し、意見があがっていた。行政は、個別案件について
左右されないのが原則になる。一方で、バスは、個別の案件の積み重な
りが利用者数の増減、ひいては維持につながる。美松台ルート利用者の
コメントとして、正規の労働ができなくなるとの発言があった。当初
は、福祉部局の窓口に相談のうえ、パブリックコメントに提出する結果
となった。こうした個人の要望を聞いていかないと、路線改廃につなが
ってしまう。また、このバスがなくなると勤務できなくなることから、
この人は勤務時間を職場で調整いただいて雇用継続となった。バスダイ
ヤ変更だけで、毎年こうした悩みが続く。利用者数だけでなく、こうし
た事情も考慮いただきたい。障がい者の場合、地元から信頼され、本人
が生きがいをもって、所得を確保しながら仕事をしている人が、バスダ
イヤが変わっただけで職を失うことがあることから、ご配慮をいただき
たい。このほか、旧国道1号沿いの事業者に下田・水戸方面から通勤して
いる人がいるが、直通便がなくなり、ややこしくなったとの声を聞いて
いる。今後、苦情等が予想されるが、ご対応をいただきたい。
事 務 局:バスダイヤ改正については、各担当課等と連携しながら進めて参る。
会 長:今回のダイヤ改正では、福祉部局との連携(提出意見の交通部局への共
有)があったか。
事 務 局:福祉部局から直接の共有は聞いていない。本人より当課窓口に来訪いただ
き、ご意見をいただいた。
会 長:定期的な利用者に最大限尊重されるよう、調整が難しいことは理解する
が、ご配慮をいただければと思う。
パブリックコメントは、6名から提出があった。人数の多寡にこだわりは
ないが、こうした計画策定にかかるパブコメでは、意見提出が多いと受
け止めていただければと思う。
今回、滋賀バス湖南野洲線について、地域間幹線系統補助の活用を協議
のうえで取りやめたことについて、伺いたい。補助をもらえるものに対
し、申請を見送った理由はあるか。
事 務 局:国庫補助は、湖南市としても活用したい思いがあった一方で、当該系統は
滋賀バス株式会社の任意路線であり、滋賀バス株式会社での調整の結果、
国庫保持所申請見送りと回答をうけた。この内容は、野洲市とも協議のう
え、滋賀バス株式会社の回答を尊重することとした。
会 長:国の制度が面倒だとか、望ましい制度ではない、といった理由か。補助
制度が利用しにくいのであれば、制度自体の改善の声を上げることもで
きる。
委 員:社内での協議の結果、国庫補助申請を申請して地域間幹線系統に認めら
れた場合、運行計画の変更が難しくなる。また、申請にあたる事務作業
に対応できる人員が社内にいない。運転士以外に事務方も担い手が不足
している。こうしたことが理由である。
会 長:国庫補助をもらうと路線を廃止・減便しにくくなるとのことと受け止め
た。制度上は、そうした縛りがあることについてもみなで共有いただけ
ればよい。補助をいただくと義務が発生する。また、申請書類の手間を
要する。このほか、国庫補助を100万円もらったら市からの補助が100万
円減少するから意味がない、ということはないか。
委 員:ご指摘の状況はない。
会 長:今後、運転手不足により、歴史と伝統のある路線であるが、やむなく路
線廃止せざるを得なくなった際、「なぜ補助をもらわなかったか」議会
や市民から言われ、この会議での対応についても問われる。大阪府で
も、路線廃止に際してそうした事例があった。その際、理由として、当
該補助額では維持が難しかった、とか、補助を受けることによる経営の
自由度低下、申請資料作成の手間が問題となったという理由を明言され
たということを記録として残したい。路線廃止となった際は、この会議
や会長である私が責任を負うことにもなる。数年後であれば皆が事情を
記憶しているが、10~20年後に廃止となった際、国庫補助を受けないこ
とにかかる経緯が不明である(当時の資料がない、担当者が不在等)、
とならないよう、議事録や次期担当への引継ぎ資料として残していただ
きたい。私も元気な限り記憶をしておく。何かあったときに、過去にさ
かのぼって「なぜあの時対応しなかったのか」経緯が分からなくならな
いよう、記録として残したい。国庫補助の活用有無は会社判断であり、
私は何も言いようがない。「湖南市地域公共交通計画(案)」に対する
意見はあるか。計画策定後には、計画を実施するミッションがある。計
画策定で終わりではなく、記載事項の実現に向けてみなで汗をかく必要
がある。
部 会 長:パブリックコメント結果にかかり、4頁の意見7.について、「市民の声が
届いていない」という思いがあると受け止めた。事務局としての考え方
は、回答列にあるとおりと理解する。事務局として、市民が地域公共交
通の取り組みに参画していく仕掛けづくりやアイデアがあれば、教えて
いただきたい。アンケート実施、場の設定等も一方策と考える。
事 務 局:パブリックコメントでは、地域公共交通計画(案)に対するものとあわ
せ、コミュニティバスダイヤ改正に対するものが多くみられた。全体の計
画より、普段の移動が気になるとの声が多かった。ダイヤ改正にあわせ、
地区での説明会等を開催していると、「ダイヤ改正前に意見を聞いてほし
い」との声があった。今回は、運転手不足から、ご意見をうかがっても反
映が難しく、こうした事後報告となった。今後は、地域公共交通計画に
基づき、新たなバス交通体系に対する意見集約の場を設定していく方向で
検討したいと考えている。
会 長:ダイヤ改正は、大変な苦労と想像する。自分の家の前のことには言いた
い放題だが、「困る」といっても乗っていないことが可視化されてい
る。今年度、利用実態が可視化されたことを踏まえたダイヤ改正と理解
する。利用実態に基づき、定期利用者を重視しつつ、JR草津線の活性化
が最重要である。そのうえで、担い手不足による便数の制約がある中
で、ダイヤ改正後も、調整をしつつ落としどころを見つけるしかない。
利用者に対するアンケートを実施いただきたい。通勤者、通学者の意見
をはじめ、利用者の意見を把握し、反映していっていただきたい。
京都府南部では、1時間に1本のバス、電車があるが、ほとんど利用がな
いのでバス事業者から廃止の提案があったところ、住民から反対の声が
上がった。令和6年度は、行政補助により継続することとなった。住民か
らは、「アンケートを実施してほしい」といった声があがってきた。前
年度には、地域公共交通計画策定のなかで住民アンケートを実施してい
る。その結果、「自家用車移動が最高である」という意見が多いとの結
果が得られている。住民アンケートを取って、自治体予算を食いつぶし
てどうするのか、興味深くみている。そうしたことになる前に、まずは
利用者のご意見を把握いただきたい。
今回は、「この時間にバスがないと私は働けない」といった切実な声が
あった。声は届けにくいため、地域懇談会等では、まず利用者の声を集
められるとよい。この町は人口がまだ多く、若い方も多い。通勤先もあ
る。この地域は、今後地域公共交通を誰も使わなくなるまちではなく、
ポテンシャルが高いまちである。定期的な利用者増加に力を入れていた
だきたい。地域公共交通の時刻表にあわせた生活を送ることは苦痛であ
るとの声もあるが、利用していくと大きなストレスはなくなる。少しで
も利用に繋げられればよい。
部 会 長:モビリティ・マネジメントの取組は様々にあるが、自家用車利用者、現役
世代からするとなじみがない。仕掛けづくりが重要である。市民に「利
用してください」というだけでは利用につながらない。懇談会等で、意
見を踏まえたバス乗車体験会実施や、社会福祉協議会と連携した外出支
援など、おでかけの視点から目的づくりを進めることなど、通勤通学の
利便性向上等が必要になる。地域公共交通会議としては、よりよい地域
公共交通にしていきたい。市民には「乗らず嫌い」の人も多い。こうし
た方々に最初の一歩を踏み出していただくきっかけづくりは、交通部局
以外の協力も必要と考える。
会 長:乗車体験会は面倒だが、数人でも行動が変わると、まちへの影響は大き
い。バスや鉄道で草津市まで行ってお茶を飲む会でもよい。電車に乗っ
ていただくことも重要である。その際、ICOCAの利便性や、モバイル
ICOCAのポイント還元もある。人によっては心を揺さぶられる取組もあ
る。そうした情報とセットで進められればよい。
委 員:計画には、利用促進の内容として、高齢者無料乗車券の記載がある。こ
れは、不健全である。なんとかならないかと思っている。行政として、
長い目でどのように考えているか。
事 務 局:高齢者無料乗車券は、各地区での説明会の際、同様の意見をいただいた。
高齢者として無料券をもらったが、無料ではいけない、対価を払うべき、
との声があった。現行制度として計画に掲載しているが、地域公共交通施
策より福祉施策としての側面が強いことから、市としてよりよい制度設計
にむけ、部署横断的に検討していきたい。
会 長:お試し利用としての無料化はよい。商業施設の開業時に洗剤を配るのと
同様である。それ以降は、有料化しなければモラルハザードが発生す
る。モラルハザードに対して、自治体が補助できる体力があれば自治体
判断となる。京都市では、高齢者になれば無料のバスに乗れる施策を継
続してきており、若い世代の税金がこの取組に使用されている。年収700
万円以上の人でも購入できた。これを無料から250円に改定しただけで大
変な苦情がきた。非課税世帯であれば、月750円の支払いで1万円以上す
るフリーパスが購入するが、取得率が大きく下がっている。一度無料と
してしまうと、モラルハザードが発生する。一定程度は、受益者負担が
望ましい社会のあり方と考える。「無料では心苦しい」という人がいる
のは、そのとおりである。高槻市では、かつて70歳以上無料のパスを発
行していたが、「混雑しているときに無料パスを呈示するのは心苦しい
から利用しない。“申し訳ない”という気持ちで利用したくない」との声も
あり、現在は運賃半額となり、一定の利用者負担を求めることとなっ
た。今のこのまちの高齢化率を踏まえながら、社会にあわせて制度を変
更していくことも公共セクターの役割である。継続検討いただきたい。
会 長:他に質問、意見はあるか。本計画についてご承認いただけるか。
一 同:挙手全員
会 長:本議案は、承認とする。今後は、計画の推進にむけ、皆さまのお力をい
ただきたい。
3.その他
事 務 局:委員より発言があるか。
委員(支局):計画書89頁にある地域公共交通の担い手確保について、幹線補助を
受けないという話の中で言及があったとおり、書類を作る人も不足してい
る。人員不足は、輸送に限らず多分野で生じている。なぜ不足しているの
か、関係の皆様で考えていただきたい。担い手不足について、事業者によ
る募集では見にいかない。湖南市では、一定の人口があるなかで、運転士
としての地域貢献など、運転士の地位向上に取り組めるようご検討をいた
だきたい。
事 務 局:交通事業者と協議しながら担い手不足への対応を進めて参る。
委 員:バスダイヤ改正について、4月1日は回数券購入で市役所窓口が混雑し、
本来の市役所業務に支障が生じている。また、時刻表作成等でも人手が
不足していると聞いている。対策はあるか。
事 務 局:市施策として進めて参る。今年度当初には大きな混乱がなかったが、来年
度にむけて体制強化を図りたい。
4.閉会あいさつ
部 会 長:本日は、地域公共交通計画策定について協議いただいた。皆様には、会議
等で多くのご意見をいただき感謝する。地域公共交通計画策定はここがゴ
ールではなくスタートである。ここからが湖南市の地域公共交通施策のス
タートである。地域公共交通施策のひとつのよりどころとしての計画書が
できた。要望等をうけつつ、この計画書をもとに対応を具体化できればよ
い。地域公共交通計画のとおり、“みんなで創る”という考え方が重要にな
る。行政、交通事業者、市民等がどのような役割を担うのか。行政や交通
事業者のみで地域公共交通を維持できなくなることは、ネガティブな面だ
けではなく、皆が自ら作っていくポジティブな転換点にもなっている。単
なる公共交通政策としてだけでなく、福祉・医療政策等の他分野との連携
が重要と考える。個人的には、現有資源の最大限の活用等にむけ、新たな
モビリティを皆で考えていくことが、今後5年間で重要となってくると考
える。今後も、皆さまとご意見を交換しながら、より良い地域公共交通を
創っていきたい。
事 務 局:本日の会議を終了する。
以上
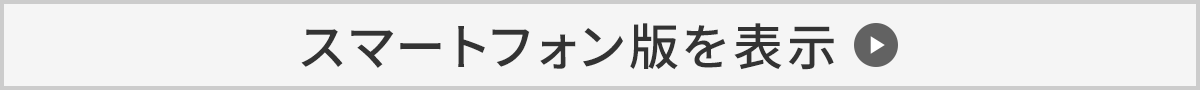








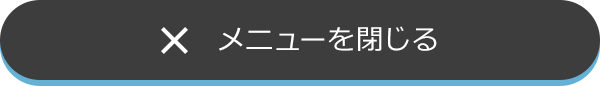




更新日:2024年04月23日