第2回湖南市文化芸術振興会議
第2回湖南市文化芸術振興会議会議録(要約)
令和6年(2024年)8月8日(木曜日)に第2回湖南市文化芸術振興会議を開催しました。
事務局:
ただ今から第2回湖南市文化芸術振興会議を開催します。開会にあたりまして、総合政策部長よりご挨拶申し上げます。
(総合政策部長あいさつ)
事務局:
それでは会議にあたりまして、最初に資料の確認をします。
(資料確認)
それでは次第に沿って会議を進めさせていただきます。まず初めに、座長よりごあいさつをお願いします。
座長:
(あいさつ)
事務局:
4月以降、一部の委員について交代がありました。いずれも所属団体の構成員の変更に伴うものです。今年度はじめの会議でもありますので、委員の皆様に自己紹介をお願いします。
(委員の自己紹介)
引き続いて、事務局にも人事異動がありましたので、簡単に自己紹介させていただきます。
(事務局の自己紹介)
それでは議事の進行につきまして、座長にお願いしたいと思います。
座長:
それではこれから議事に入ります。まず、湖南市文化芸術振興会議スケジュール(案)について事務局から説明をお願いします。
事務局:
湖南市文化芸術振興会議スケジュール(案)について、前回からの変更箇所をご説明します。まずは、それぞれの会議について、会議内容を追加し、策定までの協議の目安が分かるようにしました。計画案確定後の関係各所への意見照会やパブリックコメントなどの市側の手続きと、第5回会議を追加しました。なお、「教育委員会意見聴取」について、少し説明をさせていただきます。国の文化芸術基本法により、市長部局が計画を策定する場合は教育委員会への意見聴取が必要となります。当市は、文化行政が市長部局にありますので、意見照会やパブリックコメントに加えて、この手続きが必要となります。
座長:
私としては、追加された「教育委員会の意見聴取」ですが、前回の会議の中で、文化芸術振興に関しては、これは子どもたちの教育と非常に関わりが深いので、その点を大事にしなきゃならないのではないかと委員の方からも意見が出ていましたが、これは大変必要なことだろうと思います。他に何かありますか。もしないようでしたら、最後にまた全体的な視点からご意見が出てくるのではないかと思いますので、次に進めさせていただきます。では2番目の計画素案について、事務局の説明をお願いします。
事務局:
では、計画素案について説明します。本日は、計画の骨子についてご意見をいただきたいと考えています。計画素案そのものについては、内容説明としてご覧いただければと思います。最後に時間がありましたら、計画素案についても、少しお気づきの点などを伺っていきたいと考えています。
本計画につきましては、国の文化芸術基本法第7条の2に基づいて、地方文化芸術振興基本計画として、国の文化芸術推進基本計画、そして滋賀県文化振興基本方針を踏まえながら策定していく予定をしています。まず、計画名の案は、国・県の計画名をベースに、県内他市の計画名も参考にしながら、今のところシンプルに「湖南市文化芸術振興計画」としています。次に、計画の構成案ですが、こちらも基本的には国・県の内容を踏まえたものとしており、国・県と同じく5つの章で構成をしています。次に、目標案についても、国の文化芸術基本法に基づき策定された、国の計画や県の基本方針を踏まえた内容としています。本市の目標のあり方としては、国や県の目標や施策の方向性を踏まえつつ、より市民に近いところである基礎自治体として、地域に根差した目標となることを目指していきたいと考えています。
続きまして、計画素案について簡単に説明します。本日はたたき台としてお示ししました。章構成や目標については先ほどご説明したとおりです。内容につきましては、国や県の内容を踏まえつつ、湖南市の現状などを盛り込んだものになっています。
座長:
皆さんのご覧になった範囲で、ご質問、ご意見がありましたら伺いたいと思います。
委員:
若手の育成とか子どもの文化活動を促進するということですが、国で古典の日を11月1日に設定しています。できたら、湖南市でも11月を基本に古典文化をテーマに音楽の授業に取り組んでいただければ、文化協会としても応援したいと思います。この点も、取り組みの中に加えていただければと思います。
委員:
古典に関わらず、近くで見ることが子どもたちにとって影響があるというか、刺激になるというのをすごく感じています。計画の中にもアウトリーチ事業の取り組みがあって、すごくいいと思いました。自分の空間に来てもらって、近くで見る、可能であればちょっと触らせてもらうというのを経験すると、例えばテレビで見たりとか、まちでパンフレットを見たときに、「あのときのあれや」っていうのがすごく繋がってくるのではないかと思います。
委員:
びわ湖芸術文化財団では、びわ湖ホールと米原の文化産業交流会館の2つの拠点を持っていて、いずれもアウトリーチ活動をしています。文化産業交流会館では、「和のじかん」といいまして、古典芸能でアウトリーチ活動をしています。例えばそういう「和のじかん」をご活用いただいてもいいのかなと思いました。
座長代理:
ボリューム的にはこれぐらいかと思いますが、もう少し書き込んでもいい部分があると思います。例えば、「文化芸術をとりまく状況」について、国・県の動向を事実内容を時系列で書いていますが、もう少し中身について書いた上で、国・県と共通の課題は共通の課題として、湖南市特有の課題は特有のものとして整理しながら、「湖南市の状況と課題」へつなげていただくというのが1点です。それからいろんな言葉が出てきますが、それについて「注」という形で後ろにまとめるか、欄外に掲げるかして、詳しく知らない方でも読めるような計画にしていくと良いと思います。
事務局;
貴重なご意見ありがとうございます。特に湖南市の特徴といたしまして、障がい者の方の施設が多いということもありますし、市役所の玄関にも障がい者の方の絵を飾っております。その辺を基本理念の中にもしっかり書いていかなければならないと思っています。県では「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」に基づいて計画を策定されていますので、その辺をしっかりと書いていきたいと思います。
座長:
この計画ができたということは、同時にそれが、実際に実現するにはどうしたらいいかということになって、それがないと単なる意見だけになってしまうわけです。
委員:
計画ができて文化振興するかって言ったらそうではなくて、これはあくまでも計画なので、実行することを並行して考えていかないと駄目だと思います。この計画ができるのに1年かかります。この1年間文化が停滞していいのかっていうと、そうではないはずです。そこも踏まえて、今現状この湖南市の文化をどう進めていくかっていうのも並行して考えていただければと思います。
委員:
分野として、「芸術」「メディア芸術」「伝統芸能」「芸能」「生活文化等」「地域における文化芸術」というのがありますが、私どもは、例えば、生活文化とコラボをしたりしています。琵琶の演奏に合わせて、生活文化であります茶道とか書道とかと一緒に舞台で発表したりしています。できたら私たちも高校生とか中学生の方と一緒に舞台に立とうという思いですが、学校に結構壁があるというか、気安くお願いできないということがあります。教育委員会なり、簡単に相談できるような施策あれば嬉しいなと思います。
座長:
これは具体的な実行の問題です。おっしゃったように教育委員会が仲介の役割を果たすというのは、あり得ると思います。そういう仲介ができるというようなシステムがあれば、円滑に古典だけでなく芸術全般を教育の中に取り込んでいけると思います。そのためには場所の設定が必要です。今、湖南市の場合は、例えば美術展も美術館がないので別の会館でやっています。そういう中で場所をどう整備していくか。さっきは予算の問題が出ました。予算をどのように文化芸術振興に向けて得ていくかという問題、それから仲介の問題、それから場所の問題もあります。経済的にうまくいっているときはいいけれど、うまくいかなくなると、ぽしょんとなるのは大体文化です。
委員:
以前もお話させてもらったように、皆さんがホールに来られるわけではありません。私どもは年に数回、地区公民館に出前という形で回っています。
事務局:
本日は計画の骨子をお話いただけたらと思います。計画ができていく中で変わっていくのかもしれませんが、大まかにこの章立てでいいのか、目標についてもこの方向性で良いのかっていう部分はいかがでしょうか。
座長代理:
具体的には第3章の3、「SDGsの観点」という項目がありますが、ここについてちょっと説明をいただきたいと思います。
事務局:
SDGsにつきましては、平成27年6月に国連サミットにおいて全会一致で採択をされ、誰1人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けて、2030年を年限とする17のゴールと、169のターゲットから構成されています。本市は令和2年7月にSDGs未来都市として、内閣総理大臣から認定を受けており、文化芸術の分野においても、持続可能な社会の実現を目指していくことが市としては一貫した方向性と思っています。その中で、17のゴールのうち、4と10と17が今回の計画に関連するものとしてお示ししています。
座長代理:
第5章が「計画の推進に向けて」ということで、体制あるいは進捗管理について書いてありますが、どのように進捗管理していくのかということを説明した上で、ここについても検討したらどうかと思います。
事務局:
素案には、市民に期待される役割、そして市の役割を書いた上で、それを皆さんでどうやって推進していこうかということを書いています。例えば、この文化芸術振興会議において、毎年、進捗を管理する部分として意見を求めていきたいと思います。そして、そこで得た意見については、庁舎内で連絡調整を行いながら、次年度に向けて、足りない部分があれば、そこに力を入れる方策を検討したりしてやっていきたいと考えています。
座長:
章立てとか、その内容についてはあまり意見はありません。このまま進めていただければよいと思います。たださっきから話題になっているのはこれをどう実行するかということ。それから人材という点でも、湖南市のこういう政策に協力していただける方を見つけて、参加していただくことが必要です。
委員:
私は書道の活動をしています。実は滋賀県の小学校の書道は全国から見ると特異です。基本的に教科書に準じた授業がなされていない。何でもやったらいいよっていう感じになってしまっているのと、あとは教室の中でパフォーマンス化していると思います。楽しいというのはきっかけとしてはいいのですが、教科書に準じながらやったらこういうメリットがあるよっていうのをやっています。
座長:
滋賀県の子どもたちの書の特異性について具体的にお願いします。
委員:
学校でもルールの中での自由さがあるように、文字には本来ならば意思を伝達する、伝えるということがありますが、書道が嫌いになったら困るということで、あまりそれを強調しません。実は高校になると書写から書道に変わります。その時にものすごくギャップを感じてしまっている。先生もどう指導したらいいか分からない。例えば、中国とか日本で素晴らしいとい言われる古典があります。それを臨書しましょうっていうのは、その見えたままに書く、その次に初めて感じたものを書くってことになります。なのに、見えたままをやらないで、いきなり感じたままをやりなさいってまっています。書けない人はそっから逃れていきます。挑戦するっていうことも、ちょっとやって欲しいという感じはあります。
座長:
時代によって教育方針が変わります。60年代、70年代は、前衛書道がすごく流行って、上手に書くというより、元気なほうがいいという書道が溢れかえっていました。最近は教科書の傾向を見ると、非常にまとまりのある字を書かせたほうがいいとなってきています。そういう時代の変化というものがあります。それともうひとつは、教科書を見てますと、古典の学習に対する意識がちょっと薄い。古典は教科書にも必ず出しているんですが、しかしながら、綺麗に書かせるほうに意識がいって、古典がどういう意味を持っているかという深い意味を教えるところまではいっていない。それは国語のほうに任せている。そういうふうな点は、教科書全体の問題かもしれない。
委員:
湖南市には、まちづくりセンターが各場所にあって、そういう出来合いの建物を使って、音楽をしていただけると、聴く人も増えるのかなと思います。
委員:
子どもたちがこういう文化的な事業に関わるには、自分たちでは行けないという物理的なハードルと、やったことがないことに参加するには勇気がいると思うので、心理的なハードルがあると思います。湖南市の学校の特色として、地域と学校が一緒に子どもたちを育てるコミュニティスクールというのがあります。いろんなところで地域の人が手伝ってくださってて、教員も地域の人の顔を覚えていますし、地域の人がつなぎ役になってもいいんじゃないかなあ、コミュニティスクールっていうしっかりした団体があるので、そういうところを拠点にするのもいいのかなって思いました。
それと、子どもにとって分かりやすいきっかけというか、実際その場に行って、本当に音楽とか芸術の良さを感じる前に、お菓子がもらえるとか、何か子どもたちにとって入りやすい魅力的なきっかけが地域にあると、子どもたちにとって物理的にも心理的にもハードルが低くなって、必然的に大人になったときにホールに足を運んでみようか思うのかなと思いました。
座長:
これはひとつのヒントですね。湖南市は、9つの小学校、4つの中学校があって、ここ10年以上努力して、それぞれの学校がコミュニティスクールになって、地域の人々の協力を得るという形になりました。教員と地域との連携関係は、他の地域よりも非常にうまくいってます。こういうことが実現の可能性を上げていきます。それが湖南市の独自性のヒントとなると思います。
事務局に聞きますが、今後どのように進めて行いくのかを説明いただくと、次回我々が集まるときに心づもりができます。
事務局:
今日は大変貴重なご意見たくさんいただきましたので、ご意見をもとに素案を練り直したいと思います。次の会議は10月を予定しています。次の会議でもまだ素案ということで考えています。またそこで見ていただいて、もう一度ご意見をいただいて、そして次の会議のときには素案の「素」を取って、「案」に仕上げていきたいと思います。
座長代理:
基本目標1、2、3というのがありますが、県とかに比べて割とキュッとまとまっています。もう少し中身を分かりやすく言葉にしていただくほうがいいと思いました。
それから、今日、あまり意見が出てなかった点で、人材育成という部分がありますが、これは大きなポイントの一つだと思うので、もう少し協議していきたいと思います。
それから目標3のところでSNSがあります。これについては2点あって、ひとつはコロナでリアルなものを楽しむことができなかったときに、SNSを通じて文化芸術に接することができた、すごくアクセス数が増えたということがあって、そこら辺はもう否定できないと思います。当然そういった展開も考えていかなければならないと思います。それから、若い人のほとんどが情報をSNSで取ることが多いので、新聞あるいは市の広報も活用すればいいと思いますが、それ以外のSNSを通じた情報発信を考えていくことも、少し論点として入れたほうがいいと思いました。
座長:
今のは結構大切な意見でした。若い人たちに、市の情報をキャッチしてもらう方法を検討していくことが大切です。それと、人材育成という点です。例えば、どういうことが顕著になっていくかというと、いわゆる美術に関する愛好家は減っています。なぜかっていうと、日本では基本的に印象派を中心にした美術愛好家が多いです。その人たちが年を取ってきて、それ以後の新しい美術に対しては、ファンが分散しています。その辺も考慮に入れた上での芸術を広く考える時代が来ています。それで素案にも、メディアという分野を芸術に入れているわけです。これは今後大切になってくると思います。
いろいろご意見いただきましたけども、ご意見ないようでしたら、今日は終わりにしたいと思います。本日は皆さんご協力ありがとうございました。
事務局:
座長、円滑な進行をいただきありがとうございました。また、委員の皆様には貴重なご意見をちょうだいし、ありがとうございました。
ご意見の中でも、この計画をいかに実行するかというところがやっぱり一番重要だということだった思います。今事業をやっていないわけではないのですが、やっている中でいろんな課題がございます。今ある人材とか財源の中で、ひと工夫すれば、いろんなやり方があるのかなと感じています。今日の意見をちょうだいしまして、次回の会議で計画に触れられる部分は触れていきたいと思います。
それでは次第では、「その他」となっておりますが、事務局から少し案内をさせていただきます。
(案内)
皆様のほうから何かございますか。ないようでしたら最後に座長代理から閉会のごあいさつをお願いします。
座長代理:
(あいさつ)
事務局:
それでは以上で本日の会議を終了します。委員の皆様、長時間ありがとうございました。それでは気をつけてお帰りください。
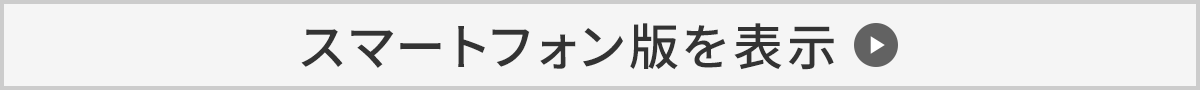








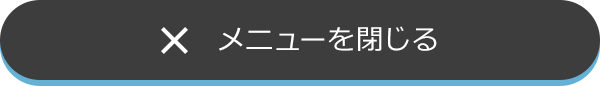




更新日:2024年09月17日