「地域住民のコミュニティ力」グループワークの結果
1月24日(金曜日)午前10時から

|
現状 |
(自治会加入) ・自治会への入会が減ってきている(若い人) ・地域の役員のなり手不足(70歳以上が多い) ・若い世代が関わりにくい地域活動 ・世代交代に不安。年配の方がすごく頑張ってくれているが下の世代にその余裕がない (ゴミ) ・通学路、雇用促進住宅周辺にゴミが多い(ペットのふんなども) (高齢化、独居) ・隣近所との付き合いが少ない ・高齢化などにより独居者や支援者が増えている ・単身者が非常に多くなった ・少子高齢化が進んでいる(空き家につながる) ・高齢者教育、100歳大学の再開 ・認知症の方が増えている (住民同士のつながり) ・家族葬が中心(個人情報も関係する?) ・特にコロナ化から人とのつながりが希薄になりつつある ・外に働きに出るお母さんが多く忙しそう。コミュニケーションを取りにくい。 ・子育て世代と年配世代とが遠慮しあって深くかかわれない ・近所付き合いが少ない ・地域の人と顔を合わせる機会が少ない ・早期就園による弊害。地域でのつながりが薄いまま就学へと進んでいく。 ・就園する年齢が低年齢化(地域で一緒に過ごせる仲間がいない) ・日中人通りが少なく特に子育て幼子を持つお母さんが孤立しやすい。 ・市役所と市民との対話が少ない気がする ・子育て家族とのかかわりが少ない ・問題が生じたとき誰に相談してよいか分からない (防災) ・防災の取組みが弱い(訓練を行っているが役に立つのか疑問) ・市に防災研修する場がない(研修は他県を利用) ・インフラが災害時にもつのか(電気、水道、ガス、通信、道路など) ・防災意識の向上化(防災士) ・空き家が多くなってきている (外国人) ・外国籍の方が多いが関わりが薄い (地域の歴史) ・地域の歴史に対する意識が少ない |
|---|---|
|
理想 |
(あいさつ) ・近所づきあいまずはあいさつから (高齢者の参加) ・独居者や要支援者の情報を公開 ・積極的に高齢の方を市の行政事業で利用活用しては (集まる場づくり) ・ゆるやかにつながれる(機会がある、場所がある) ・本格的な湖南市の道の駅をつくる ・楽しく参加できる場がある ・地域茶話会の開催 ・多世代多人種が気軽に集える場をつくる(楽しそうな場) ・市民交流の場として人付き合いのできる公園をつくる、職場、家に続く第3の交流の場とする ・ことばの壁(カーニバル) (防災) ・インフラの更新が必要。長期的な計画に基づいて投資していく ・子どもから市民全員が参加する防災研修。市の防災カレンダーを作る。 (歴史教育) ・遠足に湖南市の文化財を入れる(湖南三山・うつくしまつ) ・小学生から地域の歴史教育を進めてほしい ・大人にも市の歴史を知ってほしい |
1月24日(金曜日)午後7時から

|
現状 |
・聴覚障がい者とは ・地域との関わり(聴覚障がいに対する理解) ・コミュニティを担っている方の高齢化 ・コミュニティ力、災害時の高齢者避難 ・イベント参加者は増えているが運営側の方が少ない ・地域の横のつながり ・ろう者の老後のこと ・コミュニティ力、防災訓練(自治体、区単位) |
|---|---|
|
理想 |
・楽しい地域 ・区単位の防災訓練の実施 ・コミュニティに若い方の参加(特に20、30代)、楽しく集える場 ・手話通訳者の存在がとても重要 ・高齢者も若者も子どもも自由に集える場が欲しい。そこで新たなつながりが ・地域での情報の共有が必要では ・気軽に集える場所づくり ・誰でも楽しい生活を送れるまちに ・公園を増やす、整備された広場、子育て支援のイベントを増やす ・買い物、飲食店、なんでもしないでできる施設の充実 ・近くの公園で子どもたちの公園が聞こえるように ・すべり台、鉄棒を更新する、他の遊具等の新設 ・公園整備 |
|
その他(まとめ) |
・防災の取組みの地域差が大きい、温度差を埋める(支援する人の訓練をしているところもありそうした地域との交流) ・小さい単位の訓練により意識を高める ・公園は区や自治会が管理しているところの方がきれい、市の管理の方がだめ |
1月25日(土曜日)午後7時から

|
現状 |
・地域活動に対する市の支援が見えない ・自治会役員、民生委員のなり手不足 ・自治会に加入するメリットが無い ・自治会の加入率が低い(マンションやアパート住まいの人はほぼ加入していない) ・子育てにしても寄り添いにしてもまず自分の地域は自分たちからやっていくことから始めたい ・地域で楽しく暮らしていく為には、皆が顔見知りになっていくこと、声をかけあうことが大事と思っている ・役員も同じ人になってしまう。なり手がいない。 ・役員が嫌で自治会に加入しない |
|---|---|
|
理想 |
・地域の方々と何でも話し合っていける雰囲気づくりで防犯もしていきたい。 ・自治会加入者が減っているまた退会する人も出てきているので、業者さん、市、地区長等から自治会へ進めてもらう。 ・自治会に加入すると地域で使用できる商品券をもらえる(メリットをつくる) ・自治会や民児協の内部の活動にも資金援助があれば良い ・自治会役員の報酬を分かりやすくしてほしい |
|
その他(まとめ) |
・自治会の加入案内 自治会が担って、住民のメリットになっていることがある。(市でなく、自治会が担っている。市もそこのところで協力して) ・水戸はすすんでいると思う 今少しずつ良い方向に向かっていて、これを進めていきたい。 ・区役員など民生委員、更女、日赤などの地域のいろいろな役の人が仲良く |
1月26日(日曜日)午前10時から
グループ1

|
現状 |
・国や行政が、障がいの隔てない共生社会をめざすとうたっているが、地域で聴覚障がいの近い理解がすすめられているかよくわからない。市手話言語法を制定し共生社会をめざすために手話の啓もうを目的とした内容を広げるべきではないか。 ・地域の人たちの話し合いに入りにくい ・聴覚障がい者(高齢)の地域参加が弱い ・世代間での考え方認識がズレてる! ・グループワークの時間が少ない。もっと喋りたい! |
|---|---|
|
理想 |
・各世代への学習を広げていく。なぜ考え方が違うのか、なぜ考え方が受け入れられないのか、どんな理解が必要か。各世代の枠を超えての交流会。 ・高齢聴覚障がい者の訪問サロンを実施する中で、地域活動への参加を育成していく ・大人には簡単な手話の手引きをして! ・小中学校で手話の体験をしてみては? ・区長などリーダーが障がいがある方の存在を理解して早めに対応して欲しい ・共生社会を推し進めること。市手話言語条例を制定する ・災害時ビブスで障がい者の判別をしやすくする。 |
グループ2

|
現状
|
(消防・防災) ・消防団員募集について、人がいない ・防災について地域力が大切だと思います。隣近所と仲良く。コロナ後コミュニティ力が少なくなっている。 ・いつ何時地震が来るか分からない。 (高齢者・ボランティア) ・ハーモニカボランティア「ハーモニー」メンバーの高齢化であと5年でメンバーがいなくなる ・一人ぐらしまたは出かけられない高齢者が結構おられる。 ・高齢者65歳以上、後期高齢者75歳以上、笑顔を奪う!気持ちがしぼむ。元気が出ない。 ・高齢化が進んでいる。孤独な高齢者が増えている。 (自治会) ・地域の常会なども含めて不活発になってきている ・自治会をやめる人がいる (庁舎) ・西庁舎の部屋の使い方、無駄が多い。 (交通) ・バスをもっと通してほしい (広報) ・広報見ない (その他) ・お店が水口ばかりに集中している? |
|---|---|
|
理想 |
(消防・防災) ・積極的に広報活動をしてほしい。 ・受援体制が必要。福祉避難所の設定を進めるべき。 (高齢者・ボランティア) ・ボランティア継続のための支援。ボランティアサークルの人集めPR。支援を! ・湖南市だけでも65歳からシルバー世代、75歳からプラチナ世代、85歳~黄金世代 (自治会) ・となり近所と仲良くする ・若い人に意見を聞く ・声をかける、関係を作っていく。中間支援(市民と行政をつなげる人)重要 ・サロンを増やす ・常会等については個人の努力? (その他) ・「お店が少ない」に対しては難しい ・湖南市はちょっとしたカフェが無い。友達とお茶をしたいので近くにあるといいな。 |
|
その他(まとめ) |
・広報こなんを活用(例:ボランティアの活動報告) ・市も改善策を(ボランティア減) ・消防団活動の周知(広く!!) ・自治会で避難プランを独自に作っているのを知って!! |
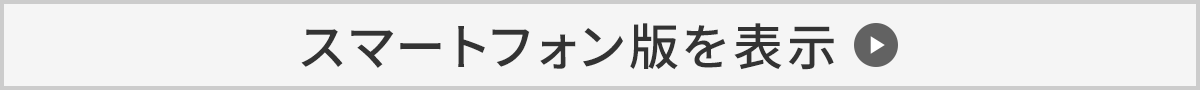








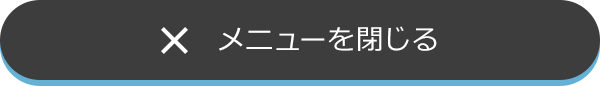




更新日:2025年03月24日