令和6年度第2回湖南市総合教育会議会議録
令和6年度 第2回 総合教育会議録
開催日時 令和7年1月29日(水曜日) 午後2時00分開議
開催場所 湖南市役所西庁舎
3階大会議室
会議次第
1 議長あいさつ
2 議題
(1)令和6年度市内小中学校におけるいじめに対する取り組みについて
(2)令和7年度湖南市教育方針についての確認
(3)令和7年度総合教育会議の時期および議題について
3 その他
(1)湖南市教育大綱の修正について
会議に出席した委員 6人
会議に出席した事務局職員 10人
会議を傍聴した人 なし
市長公室長:皆様こんにちは。定刻より少し早いですが、皆様お揃いですので、ただいまから始めさせていただきます。本日は令和6年度第2回の湖南市総合教育会議定例会にお集まりいただきありがとうございます。それでは開会にあたり、市民憲章の唱和をいたします。皆様、ご起立をお願いします。
~市民憲章唱和~
ありがとうございます。ご着席ください。続きまして市長からご挨拶をいただきます。
市長:皆さまこんにちは。着座にて失礼します。巳年の今年「蛇は古代より再生や永遠の象徴とされ、皮を脱ぎ捨て、新たな姿に生まれ変わる姿がその象徴となっています」とあります。湖南市も「新生!」の年であります。
昨年10月8日に臨時教育委員会で、私が教育長を退職することをお認めいただき、11月7日より市長に就任、この間、怒涛の日々といったところでしょうか。11月18日には、岩城委員・平松委員に辞令をお渡しすることになるとは、第1回の総合教育会議では、思いもしませんでした。また、1月1日より法山由紀子教育長に就任いただきました。法山教育長は「楽しくて力のつく湖南市教育」を誰よりも理解し、実践してきた人であることは、皆様もご承知の通りです。新体制での湖南市教育委員会には、市長部局との協働において、不安に思うことは一点もなく、期待感あるのみです。
さて、本年は4月に甲西中学校夜間学級がいよいよ開校いたします。また、9月末には、わたSHIGA輝く国スポ・障スポ2025が湖南市において開催されます。剣道、障がい者バレー等の会場として、たくさんのお客様をお出迎えすることとなります。本大会を成功させ、訪れていただく皆様に、湖南市のよいところを存分に味わっていただくため、官民が一体となって取り組んで参りたいと考えておりますので、皆様にもよろしくお願いします。
本日は、令和7年度湖南市教育方針についての確認をすることとなっています。私は、まちづくりについてのキャッチフレーズ「市民笑顔率世界一!」の実現に向けて、3つのビジョンと、12のゴールをお示ししています。その1つ「市教育方針を教育にかかわる者が共に練り上げているまち」は、市教育方針を練り上げる過程、湖南市の教育にかかわるすべてのものが主体性を持って、方針を受けとめることができる過程を踏んでいることを指します。市長として、その方針に沿って、教育の充実を図ります。
それでは、どうぞよろしくお願いいたします。
市長公室長:早速ではございますが、会議運営規則第3条第1項に「会議の議長は市長が行う」と定めておりますので、市長、議事進行よろしくお願いします。
議長(市長):では議事に入っていきます。1つ目です。「令和6年度、市内小中学校におけるいじめに対する取り組みについて」事務局お願いします。
学校教育課長:資料2ページをご覧ください。令和6年度、市内小中学校におけるいじめに対する取り組みについてご説明を申し上げます。
本市では、いじめ対策の基本的なとらえ方としまして「子どもたちが安心した学校生活を送れるよう、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいじめとする」といじめの定義をとらえ、教職員に幅広く周知し、積極的な認知を進めて参りました。本市におけるいじめの発生状況につきましては、資料にお示しした通り、今年度、令和6年度は過去最多のいじめ認知件数となる見込みです。と申しますのは、12月末現在の合計で、すでに前年度の151件を上回って、153件を認知しているということです。これにつきましては、積極的な認知を働きかけているということから、その一定の成果とも見ることができます。いじめ問題の早期発見、早期解決に繋がっていると考えられます。
発生したいじめにつきましては、事案の発生後、一旦その場では解決としますが、3ヶ月をめどに、いじめが解消されたのか、本人、保護者に直接確認を行っております。しかしながら、ご存じのように、昨年度、一昨年度といじめの重大事態案件が発生しております。一昨年度の事案につきましては、昨年度、調査報告書の公表について、新聞報道に至ったということがありまして、現在もホームページにて公開をしております。期間については、被害児童の義務教育が終わるまでとして、被害児童保護者の思いに寄り添った対応を続けております。
なお、今年度発生が大変多いいじめの中でも、特に153件中40件が加害児童生徒不明という結果が出ています。これにつきましては「画びょうを靴に入れられた」「悪口を書かれた手紙があった」などなど様々ですが、その背景にある行動に隠された、何か困りごとを児童生徒が持っているのではないかということはもちろんですが、被害児童生徒が安心して学校生活を送ることができるように、学級全体、学校全体の指導を継続しております。
また、こうしたことがきっかけで不登校に繋がることもないように、対応については、特に予防にも重点を置きながら、取り組んでいく必要があると考えております。その予防的な取り組みとしまして、児童生徒が主体となった活動、または学校や学級が魅力的なものになる活動に重点を置いて取り組んでおります。各校の取り組みについては、資料に挙げさせていただいた通りですが、こうした取り組みにつきましては、市のいじめ問題対策連絡協議会や、市の生徒指導主任主事会でも共有をし、自分たちの学校の取り組みをさらにブラッシュアップしていくことができるように指導をしているところでございます。私からは以上です。
議長(市長):はい。ありがとうございます。最初、確認ですけれども、各校の取り組みは、ちょっと後でお話しすることにしまして、それまでの全体的な取り組みについてですけれども、個別の案件も載っておりますので、このことについての議事録は、個別の個々の案件についてはホームページに載せないということでよろしいでしょうか。ですので、ここからの発言、今の事務局からの報告についても、そこの部分は載せません。ここから質問、ご意見、お願いしたいと思います。よろしくお願いします。
A委員:2ページの全体的な傾向が書いてあるんで、2ページから3ページ目にかけて、あるわけですけどね、やはり最近特に問題になってるのは、教育委員会でいつもそういうのが話題になりますけど、いじめの形が変化してるわけで、SNSを使った形での、いじめってのは非常に大きくなってきてて、その被害がある。それでその場合はフェイク情報、つまり年齢なんかを偽った形でのフェイクの情報に、ついそれに引っかかってね、いろんな被害が起こって。これはもう湖南市だけでは解決できなくて、いろんな地域に飛んでる形でそれが起こってますよね。そういう被害についてどのぐらい、この教育委員会および学校で把握してるかっていうことは、非常に大事な点だと思うんだけどその辺に関しての記述がないので、ここはちょっと少し詳しく調べとく、このいじめの件数の中に、そういうものがどのぐらい入ってきているかっていうのは、調べておく必要がやっぱりあるのではないか。もう1つはいじめっていうのは、学校の責任だけじゃすまなくて、大体家とかの間の部分で起こるんですよね。ですから把握しにくいし、防ぎにくい部分がものすごくたくさんあるんですよね。その辺がちょっと学校規格だけじゃ解決できない。大体起こってるのはその途中で起こってるから。それともう1つは個人個人のいじめっちゅうのは、そんなに多くなくて、むしろグループになっていじめる場合が非常に多い。そういういじめの特殊な形態もやっぱり把握しておく必要があると思うんですけども。その辺をやっぱりいじめを考えていくには、意識しながらいじめの形態を分析していくことが必要だと思うんです。その辺ももう少し、ここに書いていただくと、どういう状況かというのは分析しやすくなるのではないでしょうか。
もう1つはこれ件数が増えているのはさっき学校教育課長もおっしゃったけど、これは学校がちゃんと報告してるってこともある。報告しなかったらもっと少ないんですよ。そういう点では、よく調べてるってことにもなるんです。そんなことを今、ちょっと思いました。
議長(市長):はい。答えられる範囲で。それから先に言うときますけども、第1回の総合教育会議のときに、今、A委員がおっしゃってくださったような資料を前年度の資料として集約して出すということでいかがでしょうか。年度ごとにね。SNSによる、それが原因になっているとか、そこを少し見た方がいいですね。いじめの、これはもう考察になりますけども、そういったところで、第1回の総合教育会議で出してもらうということでお願いします。学校教育課長お願いします。
学校教育課長:A委員ありがとうございます。大変大切なご示唆をいただいたなと思っております。数についてお話があったように、次回ですね次年度の1回目にお示しができるようにと思っております。確かに定例の教育委員会で報告させていただいているように、LINEグループを使ったいじめ。それから、中には、端末、タブレットのTeamsの中で「乗っ取り」というような形での悪口を書き込むといったようなケースがあります。特にLINEグループ等でのいじめになってきますと、数も増えますし、拡散もものすごく早く広がっていってしまうということで、各校、対策に頭を悩ませているところでありますが、学警連携ですね、学校と警察との連携の中で、各学期必ず警察の方に出向いて、各校の状況をお伝えし、何かあったときにはすぐに相談に乗っていただけるようにという対応はとっていますが、やはり、SNS上ということで、対応が困難という事例も増えているのは確かですので、それこそ、予防的な取り組みについて、今後さらに検討していく必要があると感じております。以上です。
議長(市長):はい。ありがとうございます。他の委員さんいかがでしょうか。
B委員:すいません今のに関連してるかもわからないんですけど、ここに「積極的認知」っていうのがあるんですけれども、その「積極的認知」と「わからない」との間、いじめがないとの間にグレーゾーンってあると思うんですね。それが、どのぐらい。わからないと思うんですけど、それがいじめに繋がるか。いやいや、そこでも我慢して、もしもなんていうのかな、来れなくなったりとか、保護者の方が言ってこられてとか、また先生にそれを言ったりしたときにはこの「積極的認知」に入ると思うんですけど、そういうこと全然できなくて、心の中でもやもやもやもやしてる子どもって、案外多くいるように思うんです。そういうものはここにも上がってこないんですけど。どういう感じのとらえ方をされてるかなって思います。
学校教育課長:もうおっしゃる通りで、声を上げられる子というのは本当に一部で、割合についてわからないんですが、中には、どうしよう、思い悩んで、相談できないという児童生徒もいるという認識で、教職員には対応をお願いしているところです。そのために、各校とも教育相談アンケート、紙でアンケートをとったり、対面で話ができる先生、担任の先生に限らず、相談ができる時間を設けて、一人一人と膝を突き合わせて、困っていることはないかということや、自分のことだけではなくって、あなたから見て、心配な友達はいないかといったことも、聞き取ったり、アンケートで書いてもらったりということは続けております。そういったアンケートや面談でピックアップができるように、これも担任だけで話が終わらないように、聞き取ったことを管理職に伝える、生徒指導主任に伝える、教育相談部で話を出す、といったことができるように、これについても、生徒指導主任主事会の方で周知指導について取り組んでいきたいと思っています。
議長(市長):教育長、どうですか。この教室の雰囲気とかね。やっぱりなんか、担任やないからわかるっていうのありますよね。
教育長:担任やないからわかるっていうのわかりますね。パッと入ったときの雰囲気。この教室は暖かい空気感っていうね、ちょっとこの子の顔表情暗いなんていうのは、案外担任以外のもののが見たとき、そういうことを感じることありますね。
議長(市長): C委員、どうですか。
C委員:いじめの件数が増えているっていう、その数字だけを見ると、市民としてはすごく不安になってくるんですけども、その次の段落で早期解決に繋がっていますっていうこと、ポジティブなところも書いてあるんですけども、その事案発生後3ヶ月をめどにいじめが解消されたのかを、本人と保護者に直接確認して行っています。この令和6年度やったら153+αがどれだけ解決に繋がったのかと。それまでのことも、話が数字として出てくると、市民としては、これだけ早く発見されて、早く解決に繋がってるんやなという安心感に繋がってくるんですけども、発生件数だけが独り歩きして、どんどん湖南市ではいじめが広がってるんや、増えてるんやっていうふうに思わはる人が、CSなんかでも出て、もうその各学校の件数が増えてるんですね。いや、これは違うんですよと。小さなこともみなさんが報告しちゃうから増えてるんですって言わないと、単に数字だけが独り歩きするので、それがその後どうなったのかと、解決に繋がったっていうところも、記述があるといいかなと思いました。
議長(市長):このことについては、これもまた来年の総括をするときに、例えば、小学校129件、このうち、3ヶ月めどで、もう解消されたのが何件かとか、まだ3ヶ月に至っていないのが何件かとか、解決に至ってないのが何件かとか、ちょっとそこまで示してもらうと、それが安心感に繋がるということかなあと思います。ありがとうございます。D委員、いかがですか。
D委員:各校の取り組みなんですけど。2点お伺いしたくて。大体レベル感が、いじめのためにこういった具体的な行動していますっていうようなことを書いてくださってるんですけど。甲西中は甲西中学校人権宣言を定めていますってなってるので、何か行動をされてらっしゃると、子どもを通じて感じるんですけど、具体的な行動も先生たちの意識もいじめ対策として、こういうことをしてるっていう、まとめておくっていうのは先生たちのためにもいいのかなと思うので。レベル感をそろえてもらってもいいのかなとは思いました。あと、この各校の取り組みなんですけど、何となく年間スケジュールでこういう取り組みをする、アンケートを何月にするみたいなのを決めているのかもしれないんですけど、それを、効果があるかどうかみたいな振り返りみたいな格好でされてらっしゃるんですか。
学校教育課長:ありがとうございます。振り返りのことにつきましては、それぞれどの活動についてもそうなんですが、取り組みの後には振り返りをして、次年度にどのように改善して取り組むかっていうことは、各校で実施をしてもらっています。
議長(市長):甲西中学校については人権宣言を定めるまでのプロセスっていうのを書くということで、来年度また変えていただけたらと思います。各校の取り組みも、いかがでしょうか。ここはまた見ていただいて後程また他の方でも聞かしていただきます。そしたら次に進ませていただきます。「令和7年度湖南市教育方針についての確認」ということで、教育長お願いします。
教育長:はい、それでは令和7年度湖南市教育方針につきまして、述べさせていただきます。資料は7ページからになっております。まず、この資料で言う8ページ、湖南市教育方針の1ページにあたるところにあります、湖南市教育の構造図をご覧いただきたいと思います。令和7年度湖南市教育方針につきましては、表題「楽しくて力のつく湖南市教育」また、子どもの育つ力を信じ、夢と志を育て、「生きる力の根っこ」を太くするというスローガンのもとに、その原動力となる自尊感情を育む教育という土台に揺るぎはございません。また、湖南市教育の強みである、たて・よこ・ななめにすき間なく、どの子ももらさない指導・支援体制を大切にしながら、学校教育における取り組みの3本柱として、仲間づくりを真ん中に据えて、学びの保障とふるさと意識の醸成を図り、自尊感情の向上をめざすことに変更はございません。以上のことがより明確なものになるように、構造図にある文言の位置を若干変えさせていただいております。
さて、令和7年度の教育方針の作成にあたっては、特に当事者意識とウェルビーイングこのことを大事に考えました。子ども、教職員、そして湖南市教育に関わり、すべての人は社会形成に主体的に参画する主権者であり、地域の未来を創造し、課題解決に取り組む社会の構成員の一員であります。このことを自分ごととして、考え、そして取り組む。これがすなわち、当事者意識であります。そしてこの当事者意識を育むためには、例えば精神的に満たされてる状態であったりとか、やってみたいなっていうポジティブな感情が沸き起こったりとか、それから、自分と何か良好な関係づくりが築けていると、そういう基盤が必要だと考えますが、この基盤があってこそ、ウェルビーイングを高める必要っていうのは、ここにあるというふうに考えております。
また、この方針の定め方につきましては、先ほど市長からもありましたけれども、教育に関わるものをみんなでつくり上げるっていうことが、謳われているように、そのようにここまで取り組んで参りました。まず、教育部執行部が共通理解をしてバージョン1を提示いたします。そのバージョン1を校長、教頭、主幹教諭に示し、その意見により、バージョン2にアップ。そのバージョン2を教育委員の皆様に意見を求めさせていただいて、バージョン3へ、さらにアップ。そしてバージョン3につきましては、湖南市内の小中学校すべての教職員が読み込んで、意見を求めました。これがその意見の集約した束なんですけども、大変重みを感じているところでございます。その上で、教育長が最終的に取りまとめて、本日この会議に提出さしていただいておるところでございます。
また、教育委員会のあり方なんですけれども、湖南市教育委員会は、学校と伴走ができるように、市全体の教育の充実を目指す施策に努める。この方針にも変更はございません。
それでは個別の内容について変更した主な点をお話しさせていただこうと思います。まず、教育方針の1ページ、ゴシックの8ページになるんですけれども「はじめに」という項では、5行目あたり、「知識を活用し、問題解決に至ることにおいて、当事者意識がこれまでになく求められている」という、先ほど申しましたけれども、当事者意識という、この現在の課題を書き加えました。また、少し下ですけれども、湖南市版小規模多機能自治がめざす地域内のことを地域の人たちが自分たちで考え、問題解決策を決め、実行していく姿に、小中学校での学びが繋がっていくことを、ここで述べました。次、めくっていただきまして、2ページ目。たて・よこ・ななめにすき間なく、どの子ももらさない指導支援体制についてなんですけれども、昨年はここがどの子も漏らさない支援体制となっておりました。ただ、支援というものは、指導に伴っているものであるということから、ここのところを指導・支援体制というふうな文言に変えさせていただきました。またこの項の下の方から5行目辺りにありますように、学校が連携していくその関連機関の中に、フリースクール等の民間施設を加えました。さらに次のページになりますけれども、4月開校の夜間学級開設についても盛り込んでおります。次3ページ目、安心安全な教育環境づくりなんですけれども、先般も今後30年以内に発生確率が80%程度に引き上げられたこの南海トラフ地震について、意識ができるように加筆いたしました。さらに、近年、平均気温や最高気温の上昇から熱中症についての警戒が高まっておりますので、このことも加えました。
次に、大きな3番の教職員の資質向上と働き方改革およびハラスメントの防止の項ですけれども、ページをめくっていただいて、4ページ目になります。部活動のことについてなんですけれども、中学校における部活動、地域移行について、湖南市部活動地域移行推進計画を発信していきます、と加えまして、この一層の歩みをめざそうというふうに思います。1点申し訳ありませんが、最近名称が変わったっということで、5行目の「中学校における部活動は地域へ移行するという方針が示されています」の次なんですけれども、「市部活動改革推進協議会」っていうふうに書いてあるんですけれども、名称が変わりまして「市立中学校の部活動地域展開推進協議会」という名称に変わりましたので、議会の提出の際はそこを訂正していきます。それに伴って、計画の名称も変わっているようですので、また、正したものをお示ししたいというふうに思います。申し訳ございません。
次、4ページ、4の項の学校教育における取組の三本柱についてです。ここの書き方なんですけれども、これまで三本柱の一本ずつの柱に、それぞれ前文ということで書いておったんですけれども、その前文の内容には、具体策が多く書かれておりましたので、もう整理統合して、本文に溶け込ませる形にさせていただきました。その中で、4ページ、両括弧1の仲間づくりの項なんですけれども、3行目終わり辺りから、昨年度までアドバイスをいただきました先生から多くのことを学びました。その学びを今後も生かしていくという意味で、教室の空気感、安心、楽しい成長、満足をますます浸透させること、このことをここに強調しました。その数行下なんですけれども、今先ほど課長からもありましたいじめのことにつきまして、いじめの未然防止、早期発見、早期対応の箇所にて、これまで取り組んできましたことが、生徒指導提要に新たに書かれた発達指示的生徒指導と内容が合致することから、改めてこの言葉を加筆いたしました。隣5ページへ行っていただいて、上から7行目あたりなんですけれども、通常学級、通級指導教室、特別支援学級、特別支援学校というのは、連続性のある多様な学びの場であるというこの現状についても、ここに加筆いたしました。
最後になりますけれども、ページをめくっていただいて、方針8ページになります。生涯学習、青少年育成の充実の項ですけれども、その項の真ん中あたりですが、社会教育による学びを通じて、市民の人づくり、繋がりづくり、地域づくりを推進しますという文言なんですが、これは地域とともに子どもを育てるという理念のもとに、このことも、湖南市版小規模多機能自治につながるということを考えて、この一文を盛り込みました。以上ですけれども、この方針に沿って、全教職員、というか、もうこの湖南市教育に関わっていただく皆様が一丸となって、この取り組み気構えができますよう、皆様からのご意見をいただきたく、どうぞよろしくお願いします。
議長(市長):湖南市教育については脈々と繋がっているというところで歴代の教育長がこれを受けて、それこそある程度まではできたところまでで、そしてもう引き継ぎをしておりますので、その教育の根幹に関わることは、変わりないという太いものがございます。それこそ多分、市議会の方に、これを示しましたら、松浦教育長から法山教育長、どういうカラーを出すんやっていうことを聞かれたら、私は法山教育長には、私がずっとやってきたこと以上に、法山教育長の得意なのはやっぱり図書を生かした教育。図書館、それから、学校図書との密な連携というのか、そしてまた、甲西図書館のリニューアルということも言ってますので、その辺りを加えてやってもらえるものと、そんなふうに期待をしております。この教育方針、皆様にも、もう見ていただいていますが、いかがでしょうか。1つとってもいいなと思ったのが、脚注がそれぞれの項目に移ったんです。これが読みやすいなっていうのがあります。いかがでしょうか。
C委員:教育方針を策定していく過程についてお話いただきました。教育委員会、教育委員、学校、校長先生、教職員の皆さんが関わって作り上げていった。そのあとのことなんですけども、例えばCSの皆さんとか、または、広く市民の皆さんとか、また当事者でいくと生徒、小学生は難しいかもしれませんけども、高学年、中学生等々もここに対する意見が出せるような何か仕組みができないかなあというふうにちょっと思ったんですけども。それでも当事者、その生徒、保護者が、受け身になってこういう方針でいくんだという、プラスそこには、皆さんがたの意見も反映させた教育方針というものにならないかなとちょっと考えたりしたんですけども。そこはその後の、ここで確定版ってなってますけども、その意見を集める方法というのはどういったことが考えられますでしょうか。
教育長:大変さらに前向きで建設的なご意見ありがとうございます。確定版と書かしていただいてるんですけども、確定にはなってない、まだ、あくまでもバージョン4かもしれません。この今、先ほど校長教頭主幹教諭とか教育委員の皆様であるとか全教職員っていうのは、ここで見たものになるんですけれども、もしこの過程の段階で、例えばCSの皆さんとか、中学生であるとか小学校高学年であるとか、それから、保護者の皆さんとか、何かPTAの方でもいいんですけれども、もう少し意見を作っていく過程で、もう1個ご意見をいただくっていうような形にするのであれば、次年度以降、作成の方針についてまた考えたいなというふうに思うんですけれども、これについては、例えばCSであれば各校校長から、学校運営協議会のときに聞いていただくとか、その中にPTAの方も見ていただけると思いますので、ご意見をいただく場を作るであるとか、それから生徒会の役員さんとかに見ていただくとか、そういう広げ方もあるなということを思いましたので。さらにこれを受けて、方針について良いものを作るのが目的じゃなくて、これをもとに、どんな教育をしていくか、子どもたちがよりよい教育を受けられるよという、そこが目的なので、何かこれをもって、こんなことができるよねっていう、それを土台にした次の1歩っていうものを考える機会として、たくさんのご意見をあらゆる場で伺えたらいいなということを思いました。ありがとうございます。
議長(市長):他ございませんか。中学生も意見聞きましたら結構読んでくれましたので、また次年度、意見を聞く場を設けるということで、新年度についてはもうこのでき上がったものを、市で言いますとホームページにアップするとか、それから学校の方では理事会の方でこれを配るとか、そういったところで、来年度の「新年度」については、もうでき上がったものということですがまた教育長の方で工夫をするということです。よろしいでしょうか。はい。そしたら次に進ませていただきます。3つ目です。「令和7年度総合教育会議の時期および議題について」ということでお願いします。
教育長:資料17ページをご覧いただきたいというふうに思います。特に問題がございませんでしたら、今年度を踏襲して、来年度もこの時期、またこの内容で、全体のこの会議を開かせていただきたいというふうに思います。
議長(市長):1回目については議題として上げましょうか。3つ目で「いじめ」。「令和6年度小中学校におけるいじめについての考察」ということで、中身とか、SNSとか、それから解消状況とか、それを3つ目の議題ということでよろしいでしょうか。はい。では提案ございましたがそれを加えてということでよろしいですか。そしたらまた、来年度の教育事業評価の重点評価項目の設定というのはまた教育委員の皆様にお伺いをさしていただいて、設定するということで共通理解をしたいと思います。以上、議事については以上ですが、何か通してよろしいですか。はい。それではその他の案件に移りたいと思います。その他「湖南市教育大綱の修正」についてお願いします。
教育総務課長:第三期湖南市教育大綱の修正についてご説明させていただきます。今年度第三期湖南市教育振興プランの策定に向けて取り組んでいることはもうすでにご存じの通りでございます。現在は教育振興プランの第4章にあたる教育振興基本計画案のパブリックコメントを実施しているところです。12月定例議会の福祉教育常任委員会の方で、パブリックコメントの実施にあたって、この教育振興基本計画案は、第3章湖南市教育大綱に基づいて策定しておりますと説明させていただいたのですが、議員の方からご指摘を受けました。資料をご覧ください。第3章湖南市教育大綱の1ページ、2社会の変化と教育の使命の1行目でございます。我が国の敗戦により終戦終結して80年が経過しましたとあるが、まだ80年は経過していないのではないかというご指摘でございました。この振興プランは、令和7年4月策定を予定しておりますので、令和7年で、戦後80年ということにはなるのですが、議員のおっしゃられた通り、いつをもってと申し上げますと、令和7年8月をもって80年ということになりますので「80年が経過しました」を「80年が経過します」に修正させていただきたいと思っております。よろしくお願いします。
議長(市長):それでは他ございませんか。それではこれで第2回湖南市総合教育会議閉会させていただきます。本日はお疲れ様でございました。ありがとうございました。
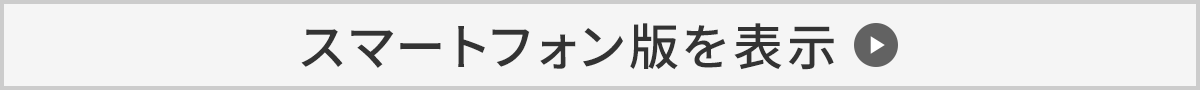








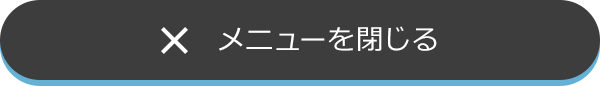




更新日:2025年02月20日