令和6年度 湖南市地域福祉推進協議会会議録
令和6年度 湖南市地域福祉推進協議会会議録
開催日時
令和6年(2024年)6月3日(月曜日) 午前10時から正午
開催場所
湖南市共同福祉施設(サンライフ甲西)1階大会議室
出席者
委員 11人(欠席者3人)
事務局 13人(湖南市7人、社会福祉協議会6人)
会議録
|
議長 |
議事の湖南市第四次地域福祉計画・地域福祉活動計画の令和5年度進捗状況について、進めていきたいと思います。 事務局から説明をお願いします。 |
|
事務局 (市・社協) |
議事を前半と後半に分け、前半は基本目標1・2、後半に基本目標3・4についてご審議いただきたいと思います。 達成度評価の基準については計画にある「施策の進捗を図る指標」および「市または社協の主な取組」の令和8年度目標に対して、令和5年度にどのくらい達成できたかを担当課で評価しています。 計画中「市民・企業に期待すること」「福祉事業所に期待すること」についての記載がありますが、令和8年度の次期策定に向け、何らかの形で評価することを検討中です。 - 基本目標1・2について、市と社協が資料に基づき説明 - 本会議開催にあたり、委員の皆さまから事前意見や質問をいただいております。 事前意見書にて、お二人の委員より進捗管理シート3ページ、1-21.地域懇談会についてご指摘いただきました。これは令和8年度の当計画第5次を策定するための地域懇談を想定しているものです。ですので、令和8年度の計画策定時期に中学校区4カ所での開催を実施予定していますが、小学校単位などの定期開催が必要との意見もいただきました。先ほども申しました、この計画にあたって「市民・企業に期待すること」「福祉事業所に期待すること」についての評価も含め、今年度か来年度の実施を検討したいと思っています。 また、3ページの「行政区交付金」について交付金の算定が一律であり区の特徴を反映できていないとの意見がありました。担当課の地域創生推進課に確認したところ、均等割・人口割・高齢割など長年積算根拠が変わっていないため、今年度に見直し予定であるとのことでした。 また、事前意見書にて進捗管理シート11ページの2-42.地域支え合い推進 会議や地域ケア会議は地域の課題や解決に必要な役割を担っていると評価をいただきましたが、その上で関係者以外の市民の認知度は高くないため、今後の展開について掘り下げた検討が必要とのご意見をいただいています。昨年の本会議の時にも、安心応援ハウスの担い手不足のご指摘や地域包括支援センターの課題についても意見をいただいておりましたので、高齢福祉課よりお話いたします。 高齢福祉課より 安心応援ハウスについてはわずかずつではありますが、開催していただける地区・団体は増えています。令和4年度の実績が26カ所、5年度は28カ所となっています。ただ、担い手不足については永遠の課題かと思っており、いかに地域の方を巻き込んで実施していけるかというところにポイントがあると思っています。あまり行政がアプローチしすぎるところがあってもやりにくいのかなと思っているので、ご相談があったら一緒に考えていきたいと思っているところです。 地域包括支援センターについては令和5年度までは高齢福祉課内に地域包括支援センターの本所があり、市内中学校区に4カ所に支所が設置されていましたが、本年度4月からはそれぞれ中学校区ごとに個別の地域包括支援センターとして委託しています。新しい体制となってこの4月からの本稼働となりますので、実績等を踏まえ、ご意見等をいただきながらより良くなるよう考えていきたいと思っています。 社協より 事前意見書では、進捗管理シート4ページのボランティア活動について、登録ボランティア団体は高齢者が多く、この先の活動が不安である、若い世代も自分の生活に余裕がない状況であるため、今後はシニア世代を中心にボランティアに興味をもってもらえるようボランティア同士の交流の場が必要ということで意見をいただいています。これについては、今後ボランティア活動の紹介や講座の開催などいかに市民の皆さんにボランティアへの関心を高めてもらうかを常に意識して取組むことが必要と思っています。ボランティア連絡協議会との連携も大切にしていきたいと考えます。また行政と協力し、ボランティアのすそ野が各地域へ広がっていくよう地域との連携も大事と思っています。 また、第2層地域支え合い事業の次のステップとして、第2層地域支えあい推進員と一緒になって活動する(仮称)第2層サポーターを確保し、活動の展開を図ることが大事であるとの事前意見をいただき、地域各所に居場所づくり、ちょっとした困りごとのサポータなどの人材が必要であると認識しています。 支え合い活動、ボランティア活動の魅力を伝えていくことが第一歩であり、地域との連携・議論の場を多く作っていきたいと思います。 また、貸付資金の指標についてこれが妥当であるのかとの事前質問についてですが、現在コロナ禍での貸付に対し、償還が始まっているところです。湖南市では利用世帯が1000世帯を超え、今後10年以内の返済になるが、フォローアップ事業により相談対応していこうと思っています。その対象世帯および令和4年度の相談件数を勘案した数値となっていることを報告します。 |
|
議長 |
基本目標1 地域活動を支える人と基本目標2 地域で支え合う力を高めるつながりづくりについての進捗状況を、ピックアップした形で報告いただきました。事前に提出いただいた質問に対しての回答に対し、さらにこの場で質問という形でも結構ですし、改めてこの基本目標に対するご意見、ご質問でも構いませんので、何かございましたらどうぞ。 |
|
委員 |
安心応援ハウス等の担い手も含め、ボランティアの数は増えているが、担い手不足は深刻であると思います。時代も変わってきているし、有償というところも考えていくべきではないか。有償の一つとしてボランティアポイント事業があるが、実施ができていない。他市など実施している現地に視察にも行ったと聞いていますが、視察に行った頃から時代も変わっており、今ですとペイペイなどのポイントを付与するなどの使いやすいものを検討したらいいと思う。時代にあった有償を考えないと経済の発展にもつながっていかないのではないでしょうか。 |
|
議長 |
確かに、指標一覧についても、ボランティアポイント事業については評価がDであり、目立っているように思います。事務局から意見はありますか。 |
|
事務局(市) |
ボランティアポイントについては令和元年ごろに検討しており、栗東市などにも視察にいったようですが、そのあと話が進まず間が空いてしまっています。その間に社会のニーズも変わっているため、ニーズ調査やどういった形が湖南市に合うかも含め、検討していきたい。ポイントの付与についても昔ながらのスタンプを紙に押すスタイルも合わないところですし、大津市では電子ポイントがあるようなので、やり方も含め、協議・検討をしていきたいと思っています。 |
|
議長 |
仕事でボランティア推進の研究をしています。ポイント制については古くから全国で紙媒体で実施されてきたという経過があるが、10年20年かけて活性化したという事例はあまりない。今の時代であるからこそ、デジタル化してスムーズに行うことが湖南市における地域活性につながるポイントとなのかと思っています。湖南市は5万人程度の人口規模なので情報伝達については、浸透が早くて有利な数字ではある。どこかでばっと盛り上がるとポイントについてはある意味流行なところがあるため、浸透しやすいのかもしれない。次年度策定までに取り組めたらいいかなと思います。 |
|
委員 |
中高生のボランティアの推進について、あるまち協では青少年育成について、年間4つのふれあい事業の一つに小学校のグラウンドや体育館を借りて、終日中学生中心に小学校高学年を対象にふれあいキャンプを実施している。中高年と比べて、青少年は瞬発力があり、素晴らしかった。広報の表紙にも取り上げてもらえ、大変良かったと思っている。こういった地道な活動を広報などで発信することで若者へ裾野を広げていくことが大事と思う。高齢者のボランティアはあるけど、塾など忙しくしている子どもがほっと一息つけるような活動をするのも支援活動といえるのではないかと思います。昨日、ニュースポーツ4種目のイベントを行った。小学校、中学校、地域が一緒になり、文化スポーツ課に登録しているボランティア10人ほどにも尽力いただきました。世代間を超えたふれあい事業は継続してやっていきたいし、広がっていけばいいなと思います。 また、社協の災害ボランティアについてのマニュアルを作ってそれに基づいて年度活動計画をたて活動を実施し、私も3年に渡って参加しました。やはり高齢者が中心となってしまうのですが、これはとても大事なことで、社協さんも頑張っておられると感じています。メンバーを揃えるのにも苦労があったと思うが、引き続き頑張っていただきたいと思います。 災害ボランティアマニュアルは毎年改定しておられ、充実しており素晴らしい。10年も経つとかなりのメンバーがそろうため、続けることが大事と思う。 |
|
議長 |
10年経つと小・中高生が20歳になり、社会を担う世代となる。そういう意味では10年というのは人を育てていくのに重要な歳月と言えます。長期スパンを意識しながら足元は毎年毎年積み重ねていくというのが大事です。 |
|
議長 |
それでは、基本目標3・4について事務局から説明をお願いします。 |
|
事務局 (市・社協) |
- 基本目標3・4について、市と社協が資料に基づき説明 - 事前意見書では、12ページの3-11.地区防災計画策定支援数の令和5年度実績0にあることに対し、地域代表社会などで説明、提案するようご意見をいただき、担当の危機管理防災課に尋ねたところ、今年度各地区で説明会を実施予定、まずは地域代表者会議にて案内予定とのことでした。 また、後段の防災士会と学区、まち協との連携についてもご意見いただきましたが、担当課より防災士連絡会において組織の見直しを検討中とのことでした。また小規模多機能自治がこの地域福祉計画に与える影響について知りたいとの意見をいただきましたので、小規模多機能自治についてお話させていただきます。 ―小規模多機能自治について説明―
続いて16ページ3-21.成年後見制度利用支援事業についての評価指標について相談会の開催を評価指標にするのはおかしいのではないかとの事前意見をいただき、課内で協議した結果、報酬助成と同じ指標に変更するよう検討します。また、後見人候補者の調整の仕組みづくりについては、ぱんじーにおいて後見人の候補者の調整を行っているため「有」としているが、仕組みとして機能できていないため、次年度からはその視点で実績を出し、成果や課題の欄に現況を記載することとします。 また、23ページコミュニティバスのノンステップ化も重要だが、令和5年4月からの減便や運行そのものの検討が必要ではないかとの事前意見をいただき担当の都市政策課に回答を求めたところ「令和6年4月のダイヤ改正については、全国的に問題になっている2024年問題といったバス運転手等の労働時間の見直しやバス運転手不足に対応するための改正でありました。当市でもバス運転手不足が深刻な問題になっており、現在の限られた人数の運転手で運行できる最大の範囲で便数、時間の設定をしているところです。今後の運行については各路線の利用状況をみながら、適正な路線・時刻設定を行い、駅と地域を結ぶ二次交通の基盤として持続可能な充実したネットワークの再構築を模索します。」とのことでした。
続いて、基本目標4について事前意見書ではこれだけたくさんの施策に取り組んでいるが、果たしてマンパワーが足りているのか数値の目標のみに追われ、市民の理解、参加意欲の熟成が追い付いていない結果になるのではないかとのご意見、別の委員からも実現のハードルの高さを痛感するとの意見をいただいているところです。施策のひとつである24ページの4-11.引きこもり支援のプラットフォームづくりについてお話をさせていただきます 障がい福祉課より 引きこもり支援のプラットフォームづくり並びに引きこもり支援については大きな課題と感じています。プラットホーム作りについてはA評価とし、令和6年度から事業開始としているところで、国の生活困窮者自立支援事業を活用し、より身近な市町での相談窓口の設置、支援対策の充実を図るということで補助金を受けながら引きこもり支援ステーションを設置しました。 こちらはひきこもり支援事業の核となる相談支援事業、居場所づくり事業、地域のネットワークづくり事業を一体となって行っています。従来は各担当課で引きこもりの方の支援を実施していましたが、市で把握しているだけで100名あまりが対象です。相談は家族からのものが多いため、まずは家族からの困りごと、どんなニーズがあるかを家族から聞き取った上で本人に寄り添った支援、一緒に考える支援が必要と思っている。 今までからも引きこもり支援に携わってくれている福祉サービス実施事業の力、社会資源も活用しながら、スピード感をもってこの事業の進めていけたらと思っています。 事業実施から3年間は実績を見ながら、地域の協力やボランティアさんの力もお借りしながら地域づくりの一環として充実していけたらと思っていますので、みなさん協力をお願いします。
社協より 事前意見では災害ボランティアについて、市民の認知度や参画意識を高めるための広報の必要性、協力者の目標未達についての意見をいただいており、まさしく社協としても協力者の固定化については課題と考えています。能登半島地震において、多額の義援金150万円ほどを届けており、市民の関心が高いと感じています。職員も災ボラ運営隊ボランティアも現地入りして支援しています。現地支援の状況を伝達するなどして、さらなる関心の高まりに期待し、新たな協力者の発掘に努めたいと考えます。 また地域権利擁護事業について、単なる金銭の預かりではなく丁寧な支援を行ってほしい、質で評価できる指標がないものか意見をいただいています。 地域権利擁護については金銭管理が一つのサービスになっていますが、数年に一度滋賀県の運営適正委員会の現地調査を受けているところです。支援内容に関しては、県の指導でも同様の指摘をいただいており、支援内容についても充実するよう考えていきたいと思っています。 |
|
議長 |
基本目標3 安全安心に暮らせる地域づくりと、基本目標4 適切な支援を届けるための体制づくりについて事務局から説明がありました。ご質問等ありましたらどうぞ。 |
|
委員 |
基本目標3の安心安全のまちづくりについて、ケアマネジャーも防災に関して、独居の方の個別避難計画など地域の方と一緒に取り組むようになっている。地域防災訓練、活動への支援が昨年に引き続きD評価であり、課題の明確化について大事ではないかと思います。実際の避難訓練については、地域で実施しやすいが、地区防災計画となるとなかなか着手しにくいのではないかと思います。課題に対する具体策など示していただければと思います。 |
|
委員 |
避難訓練の件、43区全区で実施できているかと思いますが、防災組織に民生委員が入っている区とそうでない区があると思います。私が住んでいる区では昨年、自治会から声をかけていただき、防災組織に加わり訓練に参加しましたが民生委員としての役割の重要性を感じました。普段の民生委員の活動から、独居高齢者や支援を必要とする人との関わりを行っているため、災害時想定の訓練もスムーズにできたと思う。他の区でも民生委員が入っているのかどうかお聞きしたい。 安否確認の黄色いハンカチ事業があり、個人的な意見であるが支援の優先順位もわかってすごくいいと思う。湖南市は災害が少ないので、実感が薄いのかもしれないが、ぜひ全区で取り組んでいただきたいと思います。 また、フードドライブについては民生委員の枠もたくさんとっていただき、配布すると喜んでもらえ充実感がありました。まだまだお困りの方がいらっしゃると思うのでさらに拡大していただけたらと思う。スクールガードについても、自分も含め登下校時など必要な時間は就業しているなど担い手不足の問題はあるが、できる範囲で協力したいと思っています。担い手が行き届いているのか、足りないのか教えていただけたらいいと思います。 |
|
委員 |
区で火災、防災、地震の大きな三つの災害について計画書作りましょうというのは7~8年前から地域代表者会議で聞いているが、今のところ、43ある区のうち24~25区ぐらいで取り組めているのかなと思っている。取り組もうと思っても、区の役員の任期が1~2年となると、新しい人になって変わったときに計画が立ち消えになったりして進まない現状があると思う。 積極的にやっている区はふるさと防災隊に必ず民生委員が入っていると思います。 防災士という専門知識を持つ人の力を地域でお借りできればいいと思います。市が一生懸命取り組んで200人ほどの防災士の誕生を後押しし各区に3~4人いると思うので、その方たちの力を借りて地域の防災力を高めたらいいと思います。各拠点にリーダーを起き、防災士や民生委員さんの力を借りながらよりいいものを作っていけたらと思います。 |
|
議長 |
どんな地域福祉推進にも拠点づくりが必要。各拠点にリーダーがいて、そのリーダー中心にすすめていくことが肝心。そのリーダーが防災士さんでもいいし、民生委員さんでもいい。地域の課題等に合わせて連携していけばいいと思います。行政としては、全地区が足並みをそろえて取り組めるよう旗振り役をすることが大事と思います。 |
|
事務局(市) |
避難行動要支援者については、名簿と個別計画を区が中心となって作成いただき、その内容を民生委員さんにも共有していただいているところです。今年度については、災害時に支援を要する方の優先順位をつけて、対象者を選定し、ケアマネジャーや障がいの計画相談者等の専門知識を借りながら、より個別性を高めた計画を作り、個別の避難訓練まで実施できたらと思っています。危機管理防災課に関わるご質問ご意見については、本会議の議事録を伝えることで検討を依頼したいと思います。 |
|
委員 |
防災会議、湖南市で災害が起こったことを想定に生きた訓練を実施する必要がある。43区に対し行ってほしい。区ごとで温度差があるように感じています。 |
|
委員 |
地域のふるさと防災訓練を実施したところです。近隣の山が燃えたと仮定して実施し、市の消火栓だけでは水が足りず、前の川をせき止めてそこから500メートル先までホースを25本つないで放水したが、圧力の維持など専門知識がないとできないことを実感し、地域の分団の力をかりることが必要であると痛感したところです。民生委員さんは普段の活動の中で感じておられることと思うが、地域の両隣の協力員がなかなか見つからない。高齢者は長い付き合いのなかで何となく頼める人があるが、障がい者の方の協力員が見つからないことが多いと感じている。個別の問題は地域では解決できないところも多く、行政の旗振り、先導が大事だと感じています。 |
|
議長 |
防災減災については私事ととらえやすいテーマであるため、世代を超えて取り込む必要がある。実態を把握したうえで新たな課題についても気が付きやすい。専門職の方の力をもらうというのは大事なところであると思う。行政の他部署においても連携していただく必要があると感じています。 黄色いハンカチ、防犯パトロールについては担当課に確認し、担当課や区に意見を伝えてもらいたい。 |
|
委員 |
防災士の養成に市としてご尽力いただいているが、資格取得後、地域でそれをどう生かすかの講習等がなく、防災士として地域での役割が浸透できていないこともあるように思います。318人の防災士を養成することを目標にし、10年以上前から取り組んでいることと思うが、防災士になった方も高齢になられた。このような人も登録者数に入っていると思うので、防災士としての役割を地域で果たせる人の精査をして登録するべきではないでしょうか。防災士としての知識はあるが、防災士協会からは脱退していただくような定年制とかも考えてリセットしながら登録することが必要かなと思います。 住んでいる区で情報伝達訓練も毎年実施し、その中で防災士の役割はなんだろうと模索しているところです。ご高齢の防災士の方もいて、本番で力を発揮いただけるか不安に思うこともありますので、行政の方から防災士協会に投げかけてもらえないだろうか。 実際の連絡会の参加は半分ほどとも聞いていますし、ただの有資格者ではなく、実践できる人の協会登録を先導してほしいと思います。 |
|
議長 |
防災減災の取り組みにおいても、地域福祉を担っている住民からの意見は貴重であるためぜひ担当課に伝えるように事務局にお願いしたい。福祉計画とのタイアップを強化していただきたいと思います。 |
|
委員 |
外国籍の人がいかに訓練に参加するかというところで意見を述べたい。 ある区で外国籍の方が防災士資格保持者だったため、外国籍の被災をサポートするキーパーソンになっていただけると思って関わったことがあります。JIAMで開催している外国籍の方の防災支援の研修に参加したこともあります。 湖南市、甲賀市、滋賀県、それぞれの国際協会で災害時外国人支援セミナー、防災訓練も実施しました。国際協会と県も含めてのタイアップで実施したのですが、隣の甲賀市では市とボランティアセンターと国際交流協会と三者で協定を結んでいます。将来的には市とボランティアセンターと協定を結び、国際協会と3者で頑張りたいと行政と協議をしているところです。 まち協では昨年あたりから見守り支え合いネットワークを作って、そこに民生委員も入っていただいて取り込んでいるが、区やまち協開催の防災訓練には民生委員や外国籍の方に声がかからないことがあると聞いている。外国籍の防災士も役割を求めているが、外国籍の方は自治会に入っていないこともある。区に入って初めていろんな防災も含めた情報が入ると思うので国際協会としては、外国籍の方に関してそのあたりを支援できたらと思っています。 |
|
議長 |
多文化共生の時代であり、湖南市では外国籍の人が多いのが特徴であるので、有事のときはお互い支え合う仕組みづくりが必要と思います。障がい者、高齢者など移動のしにくさを抱えた人も多いもと思うが、湖南市では津波などの被害は起こりにくいと思うので、ライフラインが分団することへの意識付けが大事と思います。どの世代にも当てはまることでもあるので、コミュニティの問題ととらえ、地域福祉と直結しているのではないかと思います。社協さんはどうですか。 |
|
事務局(社協) |
災害ボランティアセンターの運営隊を組織、平成18年の台風から自主的に結成し、マニュアルの作成もしています。昨年度、甲西北中学校区で防災フェスタがあったときにも参加してもらい、防災の意識を高めたところです。今後も意識を高くもって平常時の取り組みを進めていきたいと思っています。 |
|
議長 |
行政の指針、社協の活動というところで地域福祉計画を一緒につくる意義だと思うので、いただいたご意見を反映していただければと思います。 |
|
委員 |
コミュニティバスにつきまして、担当課からの回答をいただいたところですが、私も年に3回ほどバスを利用しています。家族から土日に運行していないと聞いてびっくりしたことがある。運転手不足、資金不足の問題は湖南市だけでなく全国的な問題でありいずれ、コミュニティバスは全国的に破綻すると思う。新しい事業の形を模索していかなければならない。野洲は自治体にて自主運営で小型バスを循環させてうまくしているとも聞いているし、成功例を集約し、湖南市の実情に合うものを探していく必要があると思います。 以前にオンデマンドタクシーの実験があったと思いますが私も利用したことがあり、メーターでは数千円の請求だったが、数百円の負担で済んだ。差額を市で負担してもらっていると思うが、大きなバスを循環走行しているよりかは安価で済んでいるのだろうがいずれにしても、今後、コミュニティバスの在り方については、がらっと方針転換する必要があると思います。 |
|
議長 |
2024年問題については国で深刻な問題となっている。移動手段の確保については、コミュニティ全体で考える必要がある喫緊の課題と思っています。担当課でも模索をされていることと思いますが、実情として移動手段の確保を市全体の方向性を検討していく必要があると思います。 |
|
委員 |
ゆららまでの定期回遊バスもなくなった。職員が運転手となり、駅とゆららまでを不定期で運行するなどいろんな方法を模索していかないとならないと思っています。 それから住んでいる地区にも地域包括支援センターができて2年になり、先日も受託先の事業所と今後の関わり方の展望などについて話し合いをしたところですが本日いただいた高齢者福祉計画について、こんな立派なものがあると知らなかった。もっと広い範囲に配布するべきと思います。 |
|
事務局(市) |
お配りした高齢者福祉計画は概要版なので、重要なポイントをまとめたものですが、いろんな関係する会議などでは配っています。全戸配布などは難しいと思いますが、地域包括支援センターや公共施設に置くなど工夫したいと思います。 障がい福祉課では「みんなで取り組むつばさプラン」を高齢福祉と同じ時期に策定しました。こちらも公共施設に設置しています。障がいのある人もない人も共に生き生き暮らせるまちづくりとしての計画になっています。右下の切れ込みに、ユニボイスというコードが入っており、専用のアプリをかざしたら読み上げてくれます。音声も男性女性、高音低音、速度も選べ、外国語にも対応していますので、ぜひご活用ください。年金の通知などにも活用されているものです。市でも広く活用していこうと思っているところです。 |
|
議長 |
ユニボイスについては、視覚障がい者向けに作られたことが発端ですが、加齢に伴い、だれしも文字を追うことが億劫になったりしますので、どなたも活用できるいいものだと思います。地域福祉計画にも搭載しているところも多いです。 本日は長時間にわたり、ありがとうございました。こうやって事務局と顔合わせができたことをいい機会に、今後も何かあれば積極的に意見などを伝えていただければと思います。 |
資料
令和6年度湖南市地域福祉推進協議会次第 (PDFファイル: 25.1KB)
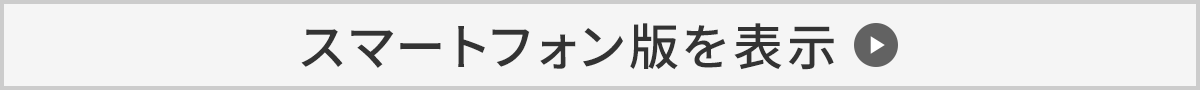








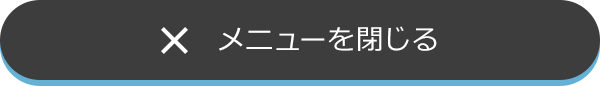




更新日:2024年08月26日